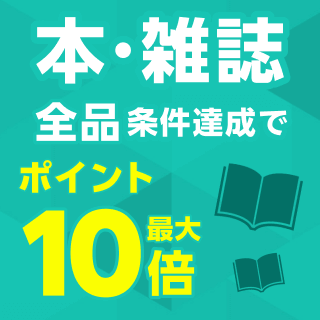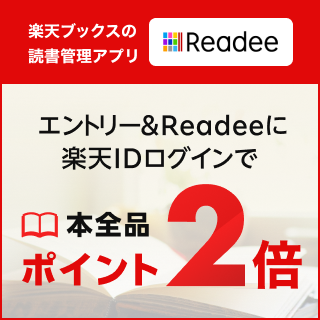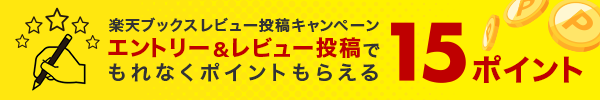猫を棄てる 父親について語るとき (文春文庫)
- | レビューを書く
726円(税込)送料無料
- 紙書籍 (文庫)
- 猫を棄てる 父親について語るとき
- 726円
- 電子書籍 (楽天Kobo)
- 猫を棄てる 父親について語るとき
- 719円
この商品が関連するクーポン・キャンペーンがあります(10件)開催中のキャンペーンをもっと見る
※エントリー必要の有無や実施期間等の各種詳細条件は、必ず各説明頁でご確認ください。
- 【楽天モバイルご契約者様】条件達成で100万ポイント山分け!
- 本・雑誌全品対象!条件達成でポイント最大10倍(2025/4/1-4/30)
- 【ポイント5倍】図書カードNEXT利用でお得に読書を楽しもう♪
- 条件達成で本全品ポイント2倍!楽天ブックスの読書管理アプリを使おう
- 【楽天Kobo】初めての方!条件達成で楽天ブックス購入分がポイント20倍
- 【楽天ブックス×楽天ウェブ検索】条件達成で10万ポイント山分け!
- 【楽天全国スーパーx楽天ブックス】最大1000円分クーポンプレゼント!
- エントリー&お気に入り新着通知登録で300円OFFクーポン当たる!
- 楽天モバイル紹介キャンペーンの拡散で300円OFFクーポン進呈
- 【楽天24】日用品の楽天24と楽天ブックス買いまわりでクーポン★
商品情報
- 発売日: 2022年11月08日
- 著者/編集: 村上 春樹(著), 高妍(絵)
- シリーズ: 猫を棄てる 父親について語るとき
- レーベル: 文春文庫
- 出版社: 文藝春秋
- 発行形態: 文庫
- ページ数: 128p
- ISBN: 9784167919528
この商品を買った人が興味のある商品
よく一緒に購入されている商品
商品説明
内容紹介(出版社より)
父の記憶、父の体験、そこから受け継いでいくもの。村上文学のルーツ。
ある夏の午後、僕は父と一緒に自転車に乗り、猫を海岸に棄てに行った。家の玄関で先回りした猫に迎えられたときは、二人で呆然とした……。
寺の次男に生まれた父は文学を愛し、家には本が溢れていた。
中国で戦争体験がある父は、毎朝小さな菩薩に向かってお経を唱えていた。
子供のころ、一緒に映画を観に行ったり、甲子園に阪神タイガースの試合を見に行ったりした。
いつからか、父との関係はすっかり疎遠になってしまったーー。
村上春樹が、語られることのなかった父の経験を引き継ぎ、たどり、
自らのルーツを初めて綴った、話題の書。
イラストレーションは、台湾出身で『緑の歌?収集群風?』が話題の高妍(ガオ イェン)氏。
内容紹介(「BOOK」データベースより)
ある夏の午後、僕は父と一緒に猫を海岸に棄てに行った。家の玄関で先回りした猫に迎えられた時は、二人で呆然とした。寺の次男に生れた父は文学を愛し、家には本が溢れていた。中国で戦争体験がある父は、毎朝小さな菩薩に向かってお経を唱えていたー。語られることのなかった父の経験を引き継ぎ、たどり、自らのルーツを綴る。
著者情報(「BOOK」データベースより)
村上春樹(ムラカミハルキ)
1949年、京都生まれ、早稲田大学文学部演劇科卒業。79年『風の歌を聴け』で群像新人文学賞を受賞、82年『羊をめぐる冒険』で野間文芸新人賞、85年『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』で谷崎潤一郎賞、96年『ねじまき鳥クロニクル』で読売文学賞、99年『約束された場所でunderground2』で桑原武夫学芸賞を受ける。2006年、フランツ・カフカ賞、フランク・オコナー国際短編賞、07年、朝日賞、坪内逍遙大賞、09年、エルサレム賞、『1Q84』で毎日出版文化賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
商品レビュー(69件)
- 総合評価
 3.64
3.64
ブックスのレビュー(3件)
-
(無題)
- ワタナツメユズ
- 投稿日:2022年11月22日
猫の話は面白かったが、本人と父の話は共感を得なかった。ちょっと難しく感じました。
0人が参考になったと回答
-
村上春樹著 久々にエッセイ読みます
- stピエトロ
- 投稿日:2022年11月10日
ポスト投函の音がしたので覗いてみると届いてました。早速読みたいと思います。
0人が参考になったと回答
-
(無題)
- とある塾経営者です
- 投稿日:2022年11月03日
村上春樹待望の文庫本です。直近の議会で猫捨てについて、エポックとなる一般質問がありましたので、比較しながら読みます。
0人が参考になったと回答
ブクログのレビュー(66件)
- 投稿日:2025年01月06日
親から引き継いでいくことについて
2024.1.6
『猫を棄てる 父親について語るとき』村上春樹 文春文庫 定価(本体660円+税) 読後感
お正月に自分の父親と義理の父親に会う機会があった。自分の父親は御年86歳。痩せ型、背も高くなく、無口。年を重ね、益々痩せて益々無口になった。高校卒業後公務員になり、定年まで勤めあげた。『真面目で実直』という言葉がピッタリ当てはまる。家族の集まりでも、常にニコニコ話を聞く係。一方、義理の父親は御年88歳。中肉中背よりややしっかりした体躯で、とにかく良く食べ良く喋る。元職業カメラマン。中国への渡航は50回を越え、『なるほど!ザ・ワールド』や『世界丸ごとハウマッチ』のコーディネーターとしても活躍、現在は4Kビデオでドキュメンタリーなどを撮っている。『明朗快活』という言葉がピッタリだ。見た目も性格も正反対の二人ではあるが、一つだけ(いや、性別とか、眼鏡をかけているとか、囲碁が好きとか言う属性を抜きにするとすれば)共通点がある。戦争を経験した、ということだ。二人とも東京に住んでいたが、空襲を逃れて片や千葉県香取郡神崎町へ、片や埼玉県比企郡小川町へと疎開した。
三が日の最後の日、村上春樹の『猫を棄てる 父親について語るとき』を読んだ。
村上春樹の父親は戦前生まれで、学生だったにも関わらず、事務手続きを忘れていて(村上春樹の父親談)、3回も兵役についたのだそうだ。
村上春樹が最後の方に書いてある一言が心に刺さった。『もし父が兵役解除されず…あるいは…もし…。もしそうなっていれば、僕という人間はこの地上には存在しなかったわけなのだから』。同じことを私も思ったことがあるのだ。
私も自分の父親や義理の父親に、戦争の話をきちんと聞いたことはない。聞くのが怖くて聞けないでいる、という方が正しいかもしれない。ただ、子供が小学生の時の夏休みの宿題で、『おじいちゃんおばあちゃんに戦争のことを聞く』というものがあった。それで、子供を通じて1度だけ聞いたことがある。父親の戦争体験を。おじいちゃんは東京に住んでいたんだけれども、空襲があって、大慌てで荷物をまとめて空襲の下を逃げて走ったんだよ、と。爆弾の降ってくる中を逃げ回って、これを逃げ切れたら生き延びられる、と思ったそうだ。運良く生き延びたおじいちゃんのお陰で私がいて子供たちがいる。子供たちはその時、この意味が、ありがたさが、分かっただろうか。その時、おじいちゃんが死んでいたら、自分はこの世に生まれてきていないんだということを。義理の父親も、米寿のお祝いの席で、疎開した話をしていた。やはり義理の父親も生き延びてくれたからこそ、旦那がいて子供たちがいる。
二人のおじいちゃんに、戦争体験を聞いておくのはとても大事なことかもしれない、と思う。村上春樹は(子は親から)『その内容がどのように不快な、目を背けたくなるようなことであれ、人はそれを自らの一部として引き受けなくてはならない。もしそうでなければ、歴史というものの意味がどこにあるだろう?』『我々は…膨大な数の雨粒の、名もなき一滴にすぎない。…しかしその一滴の雨水には、一滴の雨水なりの思いがある。一滴の雨水の歴史があり、それを受け継いでいくという一滴の雨水の責務がある。我々はそれを忘れてはならないだろう』と書いていた。自分には、二人の経験を受け継ぐ義務があると思う。
私は韓国語の勉強をしているのだが、韓国では(他のアジアの国々と同じく)旧正月にお祝いをする。旧正月の朝一番には茶礼という、日本の法事のような祭祀を行う。そこで先祖へ想いを馳せ、自分との繋がりを再認識するのだそうだが、今年は私も家族のそんな繋がりを感じる正月になった。
本は薄く、文字は大きく、文体は軽く、穏やかな語り口でさらっと読めてしまったけれども、内容はどっしりと重く、考えさせられることが多かった。お正月に家族の絆、繋がりを考えた1冊だった。高妍さんの素敵な絵が、重いテーマを少し軽くしてくれた。
♯父親 ♯家族
♯戦争 ♯戦争体験
♯村上春樹
♯猫を棄てる
♯父親について語るとき
♯本
♯読後感 - 投稿日:2024年12月28日
村上春樹さんが、お父様が亡くなったことをきっかけに、自分の父親について、そして村上さんとの関係性について、時代背景である戦争について、実際に書きはじめてみることで考えを深めていったエッセイです。台湾出身の高妍さんが担当された表紙と挿絵は、なんだかぼんやりとした思索を静かに呼ぶような絵でした。
村上千秋さんという人が春樹さんのお父様で、京都のお寺・安養寺の次男として誕生します。安養寺の住職が村上さんの祖父ですが、もともとは農家の子だったのが、修行僧として各寺で修業を積み、秀でたところがあったらしく住職として安養寺を引き受けることになったようです。
僕は読む作家を血筋で選ぶことはないので(多くの人もそうだと思います)、作家と言えば全般的に、無から生まれた有に近いようなイメージで受け止めているところがありまして(もちろんそうではない方もいらっしゃいますが)、本書のように村上春樹さんのルーツが具体化していくと、また違った世界が開けたかのような、宙ぶらりんだと思っていたものが地面に根を張っていたことに気付かされたような現実的な感覚を覚えました。やっぱり過去ってあるんだ、という至極当たり前なことを知らしめられた驚きみたいなものでしょうか。
さて。やっぱり千秋さんは徴兵されているんです。それも3度も。戦争から生き残ることも数奇な運命を辿ってのことでしょうし、運命の気まぐれのように通常よりもずっと短い期間で除隊されることも、のちに生まれる子孫のことを考えれば、紙一重みたいな運命の揺れを感じます。春樹さん自身、次のように書いています。
__________
そしてこうした文章を書けば書くほど、それを読み返せば読み返すほど、自分自身が透明になっていくような、不思議な感覚に襲われることになる。手を宙にかざしてみると、向こう側が微かに透けて見えるような気がしてくるほどだ。(p107)
__________
自分が誕生したというその出来事は、ほんとうに偶然であって、ちょっとした加減でそれは実現していないもののような、吹けば飛ぶような「事実」であると感じられる。これは、村上春樹さんだけの話ではなく、万人がすべてそうですよね。微妙で繊細な、1mmほどの運の加減で、僕らはそれぞれ、幸か不幸かこの世界に誕生している。そういった大きな運命観を感じさせられる箇所でした。
それでは、再び引用をふたつほどして終わります。
__________
いずれにせよその父の回想は、軍刀で人の首がはねられる残忍な光景は、言うまでもなく幼い僕の心に強烈に焼き付けられることになった。ひとつの情景として、更に言うならひとつの疑似体験として。言い換えれば、父の心に長いあいだ重くのしかかってきたものを――現代の用語を借りればトラウマを――息子である僕が部分的に継承したということになるだろう。人の心の繋がりというのはそういうものだし、また歴史というのもそういうものなのだ。その本質は<引き継ぎ>という行為、あるいは儀式の中にある。その内容がどのように不快な、目を背けたくなるようなことであれ、人はそれを自らの一部として引き受けなくてはならない。もしそうでなければ、歴史というものの意味がどこにあるだろう?(p62-63)
__________
→ここで言われていることを家族の間でいえば、「世代間連鎖」にあたるでしょうし、歴史という大きなものにも当てはまることとしては「連続性」にあたるでしょう。これらは、ある意味でフラクタル的(全体と部分がおなじ形になる)なのだな、というイメージが上記の引用から浮かぶと思います。なんであれ、人の営み上、負の要素も正の要素も、引き継いで僕たちは生きています。たとえば「世代間連鎖」の暴力なんかは、それを止めるのがとても難しい。でもきっと、<引き継ぎ>にはその度合いがあると思うのです。どこまで深く受容して引き継げるか、自覚的であることができるか、そういった姿勢が、<引き継ぎ>によって自らが侵食されコントロールを失う状態に陥らないためにはやったほうがいいのだろうな、と僕は考えていたりします。
__________
父の頭が実際にどれくらい良かったか、僕にはわからない。そのときもわからなかったし、今でもわからない。というか、そういうものごとにとくに関心もない。たぶん僕のような職業の人間にとって、人の頭が良いか悪いかというのは、さして大事な問題ではないからだろう。そこでは頭の良さよりはむしろ、心の自由な動き、勘の鋭さのようなものの方が重用される。だから、「頭の良し悪し」といった価値基準の軸で人を測ることは――少なくとも僕の場合――ほとんどない。(p68)
__________
→お父様は京大の大学院までいって、家庭の事情で中退されたそうです。それはさておき、ここで春樹さんがどういう価値判断をする人かが見えています。たしかに、小説を書くのに心の自由な動きがままならなかったら、説明だらけの小説になってしまいそうな気がします。勘の鋭さのようなものも、ストーリーの要となるものがどこにあるのか、それがそれまでに書いた中で後につながる要素としてもう書かれていることに気付くことができるか、みたいなことはあると思います。それとは別に、頭の良し悪しで人を判断しないという職業的性質が、他者を見る目として柔らかな目となって機能すると思えるのですが、それって、人をモノ扱いせずちゃんと人間扱いする目でしょうから、こういったところはみんなが養えるように学校教育に組み込めばいいのに、なんて考えたりしました。創作の授業をやったらどうか、ということです。
というところでした。100ページちょっとの分量の、淡々とした短いエッセイです。でも、村上春樹さんの作品をたくさん読んできましたから、知らずにできあがっている心の中の「村上さん領域」を埋めるパーツがひとつ手に入ったような感触のある読書体験になりました。こうやって最後になってからやっといいますが、「猫を棄てる」エピソードが、些細な微笑ましさを含んでいて、それが小さなちいさな救いになっていると思いました。 - 投稿日:2024年11月15日
小さい頃に父親と猫を棄てに行ったエピソードから始まり、村上春樹が調べた父親の足跡が語られている。
絶縁に近い状態にまでなった父親と、父親の死の間際に和解する際に一つの力になったのが、小さい頃のささやかな共有体験だったという話が素敵だなと思った。
どんなに拗れてしまった関係であっても、ささやかでも何か共有したものがあれば、もしかしたら修復できるのかもしれないなという希望を感じた。
お気に入り新着通知
- 未追加:
- 3件
ランキング:文庫
※1時間ごとに更新
-
1

-
【入荷予約】吉本ばななが友だちの悩みに…
吉本ばなな
660円(税込)
-
2

-
【予約】火喰鳥を、喰う
原 浩
792円(税込)
-
3

-
【予約】三河雑兵心得【十六】関ケ原仁義…
井原忠政
759円(税込)
-
4

-
一次元の挿し木
松下 龍之介
899円(税込)
-
5

-
でっちあげ
福田 ますみ
693円(税込)
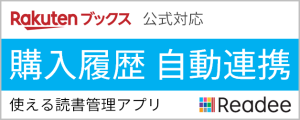



![猫を棄てる父親について語るとき(文春文庫)[村上春樹]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/9528/9784167919528_1_2.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![猫を棄てる父親について語るとき(文春文庫)[村上春樹]](https://tshop.r10s.jp/book/cabinet/9528/9784167919528_1_2.jpg)