昭和史の本質ー良心と偽善のあいだー(新潮新書) (新潮新書) [電子書籍版]
保阪正康
- | レビューを書く
836円(税込)
- 電子書籍 (楽天Kobo)
- 昭和史の本質ー良心と偽善のあいだー(新潮新書)
- 836円
- 紙書籍 (新書)
- 昭和史の本質
- 836円
商品情報
この商品を買った人が興味のある商品
商品説明
内容紹介
「国民の九割強は良心を持たない」ーー芥川龍之介の言葉を裏付けるかのように、時流におもねる偽善は、軍人にかぎらず政治家や知識人、多くの大人たちにも見てとれる。三百万を超える犠牲者を出したあの戦争、敗戦とともに始まった戦後民主主義……日本人は、いったいどこで何を間違えたのか。近現代の名作に刻まれた一文を手掛かりに多彩な史実をひもとき、過去から未来へと連鎖する歴史の本質を探りだす。
商品レビュー(5件)
- 総合評価
 3.25
3.25
楽天Koboのレビュー
まだレビューがありません。 レビューを書く
ブクログのレビュー(5件)
- 投稿日:2024年08月28日
支離滅裂。
著者80歳くらい。
雑誌に掲載されたエッセー。
著名な文学作品からの引用、そこから連想される歴史的出来事や人物エピソードなどを気まぐれに繋いだような文章。
しかし取り上げてている時代や事象に何の統一性もないため読んでいると残飯のごった煮を食べさせられているような胸焼けがする。
戦時中の戦争指導者を諫める論調が強いが,単発エピソードの羅列。
読むのが辛くなってきたが,単発歴史エピソードや作家エピソードで1つでも興味のあるものを拾えたらとなんとか流し読みした。
泉鏡花とか川端康成,芥川などを読んだら面白いのかな?ということだけが収穫。
本人,これで人に読ませる価値のある文章と思って出してるのかねえ。年取ると頭の回路がこういうふうになっていくのかねえ。 - 投稿日:2021年03月09日
文学にはその時代の社会のありようが投影される。今手に取って読む本は、作者が生きていた時代のひとつの鏡である。この本を読んで、今を生きている私は過去の歴史に立っているわけだから、自らの国や世界の歴史をきちんと勉強する必要があると強く思った。
- 投稿日:2021年02月07日
●→引用、他は感想
●かつて頭山が持っていた北海道の炭鉱が75万円で売れたそうだ。明治時代である。これを聞きつけた全国の頭山崇拝者たちが大喜びで、次々に頭山邸にやってくる。(略)頭山はどんな話にもいやと言わない。なんでも頼みを聞く。瞬くまに75万円は無くなった。(略)それでも頭山邸には居候を決め込む書生、壮士、無頼人が居残った。頭山の腹心が、こんな連中は追い出したほうがいい、そうでなければ先生の一家が野たれ死にしますよ、と忠告したという。すると頭山は次のように答えたと夢野は書く「まあそう、急いで追い出さんでもええ。喰うものが無くなったらどこかへ行くじゃろ」それまではここにいるといいさ、というわけだ。食料が尽きると、足早に去っていくだろう、と見ている。こんな連中でも食事くらいはあたえてやるがいいさ、というのは確かに大物だ。同時に景気の良い他人にたかる輩はいつの時代にもいるのであり、たかり尽くすと逃げ足だけは早いということになるのだろうか。逆に逃げ足の遅い、つまり死ぬまでその地に止まるのはよほどその地を離れるのが怖い、あるいは事情があって離れることができないということになるのだろうか。
●民俗学者の柳田国男の書(「明治大正史」)によるなら、酒を毎日飲むのは古い作法ではなく、日本の伝統的なしきたりでなかったというのだ。「以前は明らかに悪癖の一つに数えられ、今でも養生とか慰安とか、訊かれもせぬ言訳をしている者が多い」と書く。幕末に日本にやって来た外国人は識字率の高さに驚くと同時に、反面で酔っ払いの横行に驚いたらしい。自分たちと飲み方が違うというのだ。そこで禁酒運動などを起こそうとなるのだが、柳田国男は、(略)単に目の前の酔っ払いを見て、禁酒運動など進めても無理、というのである。柳田によるならば、共同体には必ず地酒の伝統があり、幕府が禁じたとしても密かにその伝統は守られて来たという。加えて酔うならなんでもいい、飲んでみようという庶民はいつの時代にもいた。やはり柳田の一文を引用して、酒飲みはいつの世も決してなくならないとのご宣託を確認しておこう。「酒が飲む者を忘我の境に誘うことは、近ごろ始まった悪徳でもなんでもない。近ごろ始まった現象は居酒と独酌の連続、それから酒が旨くなりまた高くなったことと、国家が小民の何を飲んでいたかを、ついうっかり忘れてしまったこととである」柳田は名文家である。ところが酒飲みについて触れる部分では、文章は回りくどい表現になる。「酒」が主語となる文章では、意外にも柳田先生も酒を飲みつつ書いたのかもしれない。
”近現代の名作に刻まれた一文を手掛かりに多彩な史実をひもとき、過去から未来へと連鎖する歴史の本質を探り出す”という、今まで読んだ保坂著作とはちょっと毛色が違うエッセイ集。手元に置いておいて、気が向いた時に読んでみたい本である。
楽天ブックスランキング情報
-
 週間ランキング
週間ランキング
ランキング情報がありません。
-
 日別ランキング
日別ランキング
ランキング情報がありません。
-
期間限定!イチオシのキャンペーン
電子書籍のお得なキャンペーンを期間限定で開催中。お見逃しなく!
ランキング:人文・思想・社会
※1時間ごとに更新
-
1

-
 大白蓮華 2025年4月号
大白蓮華 2025年4月号
大白蓮華編集部
224円(税込)
-
2
![アンガーマネジメント超入門 「怒り」が消える心のトレーニング [図解] (特装版)](//tshop.r10s.jp/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9387/2000010299387.jpg?downsize=80:*)
-
 アンガーマネジメント超入門 「怒り」が…
アンガーマネジメント超入門 「怒り」が…
安藤俊介
200円(税込)
-
3

-
 地面師 他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺…
地面師 他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺…
森功
363円(税込)
-
4

-
 赤と青のガウン
赤と青のガウン
彬子女王
1,100円(税込)
-
5

-
 妻のトリセツ
妻のトリセツ
黒川伊保子
413円(税込)


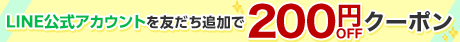












































































 電子書籍版
電子書籍版

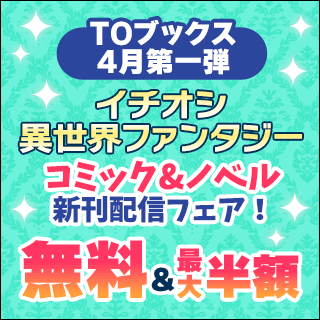





![アンガーマネジメント超入門 「怒り」が消える心のトレーニング [図解] (特装版)](http://tshop.r10s.jp/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9387/2000010299387.jpg?downsize=80:*)









