言論統制というビジネスー新聞社史から消された「戦争」ー(新潮選書) (新潮選書) [電子書籍版]
里見脩
- | レビューを書く
1,705円(税込)
- 電子書籍 (楽天Kobo)
- 言論統制というビジネスー新聞社史から消された「戦争」ー(新潮選書)
- 1,705円
- 紙書籍 (全集・双書)
- 言論統制というビジネス
- 1,705円
商品情報
この商品を買った人が興味のある商品
商品説明
内容紹介
「権力とメディアの癒着」ーーその原点は戦時統制にあり!
「軍部の弾圧でペンを折らざるを得なかった」は虚構だった。「報道報国」の名の下、部数を貪欲に追い求めた新聞社は、当局に迎合するだけの記者クラブを作り、唯一の統制機関「内閣情報局」に幹部を送り込んだ。そして、ライバル紙を蹴落とすために地方紙大合併を仕掛け……。戦争を利用し尽くしたメディア暗黒史。
商品レビュー(4件)
- 総合評価
 4.67
4.67
楽天Koboのレビュー
まだレビューがありません。 レビューを書く
ブクログのレビュー(4件)
- 投稿日:2024年12月25日
一県一紙体制の経緯が知りたかっただけなんだけどなぁと思って買ったけれど、結果的に近代の新聞史を振り返らないと一県一紙体制だけをピックアップしてもわからなかっただろうなということが理解できたので読んでよかった。
あと、地元の富山は地元紙の北日本新聞が強いわけだけど、全国紙だと読売を購読している世帯が多く、その理由も12章でわかった。
事実のみの記述が多くて著者の判断はあまり書かれていないと思う。
全体を読んだ感想としては、新聞に携わっている人たちは「新聞という会社」を存続させたかっただけで、世論とか言論とか正義とかそういうものを守りたかったわけではないんだろうなと思った。 - 投稿日:2024年01月03日
この本は非常に面白く、非常に興味深い本だった。サブタイトルの「 新聞社史から消された「戦争」」、「「愛国」は儲かる!」という帯に非常に心惹かれた。
メディアでは決して取り上げない、戦前戦中の報道を新聞を基軸として取り上げ、新聞がどのように国と向き合い、国にもたれ掛かり、国と心中したのかを、二人のメディアの巨人をベースに、話を進めている。古野伊之助 氏と、対立軸としての正力松太郎氏だ。
この二人がどのように新聞に向き合い、 国に働きかけていったかを、同盟通信社という会社をベースにして描き出している。満州で行われた言論統制という実験を日本国内に持ち込み、13428紙あった新聞を、一県一紙態勢まで持っていった。
現状の新聞にもつながっていく、戦前戦中の新聞業界がどのように作られていったかを、抉りとっていて非常に面白い。なかなかメディアでは取り上げづらい歴史と真実だからだ。戦前戦中の政治に限らず、メディア研究にも役に立つ、一級の書籍である。 - 投稿日:2022年02月07日
第二次世界大戦下の日本で言論統制があったことはある程度理解しているつもりだったが、本書で官側の規制に対して民間側の対応策に様々な駆け引きがあり、ある意味で規制をうまく利用していったしたたかな知恵者がいたことに驚嘆した.古野伊之助と正力松太郎だ.全国紙と地方紙、さらに通信社の生き残りを図るためのアイデアが続出していた.一県一紙が要請された際に、全国紙(朝日/毎日/読売)の正力と地方紙の古野の駆け引きは面白い.地方紙として東京3、大阪2だが、なんと広島は海軍の関係で2(中国新聞と呉新聞).1944.7発足の小磯内閣で、朝日新聞副社長の緒方竹虎が国務大臣・情報局総裁に就任したのが笑える話だ.
楽天ブックスランキング情報
-
 週間ランキング
週間ランキング
ランキング情報がありません。
-
 日別ランキング
日別ランキング
ランキング情報がありません。
-
期間限定!イチオシのキャンペーン
電子書籍のお得なキャンペーンを期間限定で開催中。お見逃しなく!
ランキング:人文・思想・社会
※1時間ごとに更新
-
1

-
 大白蓮華 2025年4月号
大白蓮華 2025年4月号
大白蓮華編集部
224円(税込)
-
2
![アンガーマネジメント超入門 「怒り」が消える心のトレーニング [図解] (特装版)](//tshop.r10s.jp/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9387/2000010299387.jpg?downsize=80:*)
-
 アンガーマネジメント超入門 「怒り」が…
アンガーマネジメント超入門 「怒り」が…
安藤俊介
200円(税込)
-
3

-
 ファスト&スロー上
ファスト&スロー上
ダニエル・カーネマン
1,056円(税込)
-
4

-
 マンガでわかる「すぐ不安になってしまう…
マンガでわかる「すぐ不安になってしまう…
大嶋信頼
200円(税込)
-
5

-
 既婚メス力
既婚メス力
神崎メリ
1,760円(税込)


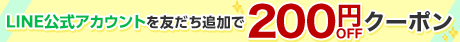



























 電子書籍版
電子書籍版







![アンガーマネジメント超入門 「怒り」が消える心のトレーニング [図解] (特装版)](http://tshop.r10s.jp/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9387/2000010299387.jpg?downsize=80:*)









