商品情報
この商品を買った人が興味のある商品
商品説明
内容紹介
「死」。それは古今東西、あらゆる思想家、宗教家が向きあってきた大問題である。「死ぬ」とはどういうことなのか。「あの世」はあるのか。「自分」が死んだら、「世界」はどうなるのかーー。先人たちは「死」をどう考えてきたのか、宗教は「死」をどう捉えているのかを踏まえながら、人間にとって最大の謎を、稀代の思想家が柔らかな筆致で徹底的に追究する。超高齢化社会で静かに死ぬための心構えを示す、唯一無二の論考。
商品レビュー(4件)
- 総合評価
 4.00
4.00
楽天Koboのレビュー
まだレビューがありません。 レビューを書く
ブクログのレビュー(4件)
- 投稿日:2021年02月23日
佐伯啓思は西部邁とは院生のときから40年来の付き合いだそうだ。その佐伯が反成長主義として、死と生を扱ったのが、この本。なので、西部の自死についても述べている点が、自分にとっては興味深い。仏教的な死生観なので、自分にとっては、受け入れやすい。仏教の「色即是空、空即是色」といった概念は、自分としては、真実であると思われる点だが、そうだとしたときに、西部は、無を考えることの無意味、無ということすらも言語であること、西部にとって重要だったのは、活動的な生と自分で自分の死を決める、というあたりを重視しての自死だったと説明する。逆に、自分は佐伯に近いが、無であることに思いをいたすこと自体は、有意味だと思う。死んだらおしまいだからこそ、いつおしまいになってもよいように生を充実させる。最後の幕引きも自分で決めるのではなく、いかに無様だろうと、生の時間をきちんとまっとうするということになるのではないか。
自分の多様性理論からすると、日本人が、無に着眼したのに対して、西洋人が、有に着眼して、哲学・思想を構築してきたというとらえ方は、自分にとって新鮮。 - 投稿日:2020年08月03日
個人的にはもうちょっと突っ込んだ内容が欲しかった。
「死」に対しての、宗教や文化の違いを例示するなど、様々な考え方があっていいはずで、それらを示しながら、あなたはどう死ぬか?(どう生きるか?)を考える内容かと思って読んだら、少し肩透かしだった。
比較的、著者の意見が真っすぐに書かれていた本でした。
人生100年時代だ。
なかなか死ねない我々。
そして、死に方を容易に自分では選べない我々。
快活に生きることはどういうことなのか?
死に方を考えることは、生き方を考えることだ。
私の死生観はこれに尽きる。
「死ぬ気になって生きろ!」どうせ死は訪れる。
ダラダラしている暇はない。
愚痴ばかり言っている暇もない。
「死の恐怖」すらも忘れられるくらい、一生懸命に突っ走れ!
ただそれだけだ。
(2018/7/15) - 投稿日:2018年11月29日
経済学の大家が書いた「死と生」
ギリシア・キリスト・西洋文明そして、東洋文明、日本文明の情報を駆使しての「死と生」、論理的でメチャクチャ解りやすく、自分なりに理解できました。
丁度、般若心経の写経を継続しており、その一字一句の奥深さがよりはっきりしてきました。
西部邁さんの「自死」にいたる経過も含め、少なからず影響を受けられてと思います。
経済学者の日本文明の解析、ますますの進化を期待している所です。
楽天ブックスランキング情報
-
 週間ランキング
週間ランキング
ランキング情報がありません。
-
 日別ランキング
日別ランキング
ランキング情報がありません。
-
期間限定!イチオシのキャンペーン
電子書籍のお得なキャンペーンを期間限定で開催中。お見逃しなく!
ランキング:人文・思想・社会
※1時間ごとに更新
-
1

-
 大白蓮華 2025年4月号
大白蓮華 2025年4月号
大白蓮華編集部
224円(税込)
-
2
![アンガーマネジメント超入門 「怒り」が消える心のトレーニング [図解] (特装版)](//tshop.r10s.jp/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9387/2000010299387.jpg?downsize=80:*)
-
 アンガーマネジメント超入門 「怒り」が…
アンガーマネジメント超入門 「怒り」が…
安藤俊介
1,430円(税込)
-
3

-
 大乗仏教の誕生 「さとり」と「廻向」
大乗仏教の誕生 「さとり」と「廻向」
梶山雄一
550円(税込)
-
4

-
 ヒルビリー・エレジー~アメリカの繁栄か…
ヒルビリー・エレジー~アメリカの繁栄か…
J・D・ヴァンス
1,320円(税込)
-
5

-
 これからの「正義」の話をしよう ──い…
これからの「正義」の話をしよう ──い…
マイケル・サンデル
990円(税込)


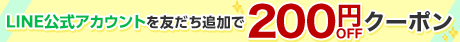
































































 電子書籍版
電子書籍版







![アンガーマネジメント超入門 「怒り」が消える心のトレーニング [図解] (特装版)](http://tshop.r10s.jp/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9387/2000010299387.jpg?downsize=80:*)









