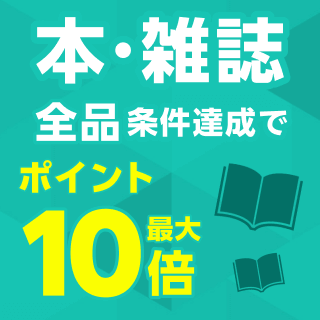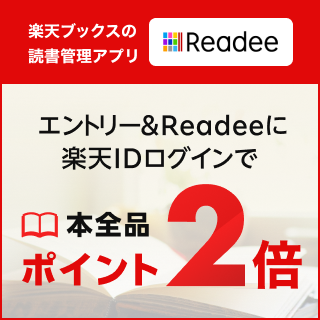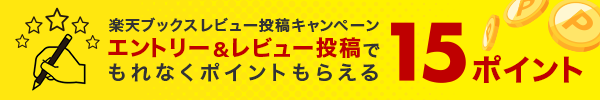- 現在地
- トップ > 本 > 医学・薬学・看護学・歯科学 > 基礎看護学 > その他
医療現場の行動経済学 すれ違う医者と患者
- | レビューを書く
2,640円(税込)送料無料
- 紙書籍 (単行本)
- 医療現場の行動経済学
- 2,640円
- 電子書籍 (楽天Kobo)
- 医療現場の行動経済学
- 2,640円
この商品が関連するクーポン・キャンペーンがあります(10件)開催中のキャンペーンをもっと見る
※エントリー必要の有無や実施期間等の各種詳細条件は、必ず各説明頁でご確認ください。
- 【楽天モバイルご契約者様】条件達成で100万ポイント山分け!
- 本・雑誌全品対象!条件達成でポイント最大10倍(2025/4/1-4/30)
- 【ポイント5倍】図書カードNEXT利用でお得に読書を楽しもう♪
- 条件達成で本全品ポイント2倍!楽天ブックスの読書管理アプリを使おう
- 【楽天Kobo】初めての方!条件達成で楽天ブックス購入分がポイント20倍
- 【楽天全国スーパーx楽天ブックス】最大1000円分クーポンプレゼント!
- エントリー&お気に入り新着通知登録で300円OFFクーポン当たる!
- 楽天モバイル紹介キャンペーンの拡散で300円OFFクーポン進呈
- 【楽天24】日用品の楽天24と楽天ブックス買いまわりでクーポン★
- 【楽天マガジン】楽天ブックスでのお買い物が全品ポイント10倍に!
商品情報

商品説明
内容紹介(出版社より)
医者「なぜ患者さんは治療方針を決められないのか」
患者「なぜお医者さんは不安な気持ちをわかってくれないのか」
人間心理のクセがわかれば、溝は埋められる!
「ここまでやって来たのだから続けたい」
「まだ大丈夫だからこのままでいい」
「『がんが消えた』という広告があった」
「本人は延命治療を拒否しているが、家族としては延命治療をしてほしい」
「一度始めた人工呼吸管理はやめられない」
といった診療現場での会話例から、行動経済学的に患者とその家族、医療者の意思決定を分析。
医者と患者双方がよりよい意思決定をするうえで役立つ一冊!
シェアード・ディシジョン・メーキングに欠かせない必読の書。
「行動経済学では、人間の意思決定には、合理的な意思決定から系統的に逸脱する傾向、すなわちバイアスが存在すると想定している。そのため、同じ情報であっても、その表現の仕方次第で私たちの意思決定が違ってくることが知られている。医療者がそうした患者の意思決定のバイアスを知っていたならば、患者により合理的な意思決定をうまくさせることができるようになる。また、医療者自身にも様々な意思決定におけるバイアスがある。そうしたバイアスから逃れて、できるだけ合理的な意思決定ができるようにしたい。患者も行動経済学を知ることで、自分自身でよりよい意思決定ができるようになるだろう。」--「はじめに」より
【主要目次】
第1部 医療行動経済学とは
第1章 診療現場での会話
第2章 行動経済学の枠組み
第3章 医療行動経済学の現状
第2部 患者と家族の意思決定
第4章 どうすればがん治療で適切な意思決定支援ができるのか
第5章 どうすればがん検診の受診率を上げられるのか
第6章 なぜ子宮頸がんの予防行動が進まないのか
第7章 どうすれば遺族の後悔を減らせるのか
第8章 どうすれば高齢患者に適切な意思決定支援ができるのか
第9章 臓器提供の意思をどう示すか
第3部 医療者の意思決定
第10章 なぜ一度始めた人工呼吸管理はやめられないのか
第11章 なぜ急性期の意思決定は難しいのか
第12章 なぜ医師の診療パターンに違いがあるのか
第13章 他人を思いやる人ほど看護師に向いているのか
内容紹介(「BOOK」データベースより)
「ここまでやって来たのだから続けたい」「まだ大丈夫だからこのままでいい」「『がんが消えた』という広告があった」といった診察室での会話例から、行動経済学的に患者とその家族、医療者の意思決定を分析。医者と患者双方がよりよい意思決定をするうえで役立つ一冊!
目次(「BOOK」データベースより)
第1部 医療行動経済学とは(診療現場での会話/行動経済学の枠組み/医療行動経済学の現状)/第2部 患者と家族の意思決定(どうすればがん治療で適切な意思決定支援ができるのか/どうすればがん検診の受診率を上げられるのか/なぜ子宮頚がんの予防行動が進まないのか ほか)/第3部 医療者の意思決定(なぜ一度始めた人工呼吸管理はやめられないのかー倫理は感情で動いている/なぜ急性期の意思決定は難しいのか/なぜ医師の診療パターンに違いがあるのか ほか)
著者情報(「BOOK」データベースより)
大竹文雄(オオタケフミオ)
1961年京都府生まれ。1983年京都大学経済学部卒業、1985年大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程修了。1985年大阪大学経済学部助手、同社会経済研究所教授などを経て、2018年より大阪大学大学院経済学研究科教授。博士(経済学)。専門は労働経済学、行動経済学。2005年日経・経済図書文化賞、2005年サントリー学芸賞、2006年エコノミスト賞(『日本の不平等』日本経済新聞社)受賞。2006年日本経済学会・石川賞、2008年日本学士院賞受賞
平井啓(ヒライケイ)
1972年山口県生まれ。1997年大阪大学大学院人間科学研究科博士前期課程修了。1997年大阪大学人間科学部助手、同大型教育研究プロジェクト支援室・未来戦略機構・経営企画オフィス准教授を経て、2018年より大阪大学大学院人間科学研究科准教授。博士(人間科学)。2010年より市立岸和田市民病院指導健康心理士。専門は、健康・医療心理学、行動医学、サイコオンコロジー、行動経済学。2007年日本サイコオンコロジー学会奨励賞、2013年日本健康心理学会実践活動奨励賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
商品レビュー(50件)
- 総合評価
 3.92
3.92
ブックスのレビュー
まだレビューがありません。 レビューを書く
ブクログのレビュー(50件)
- 投稿日:2025年02月17日
行動経済学では人間は合理的な生き物ではないということが出発点として考えられていることに衝撃を受けた。また、立ち止まって考えると、人間は合理的ではないのが当然だと思う。ただ、医療の現場、特に医者や看護師から治療について説明を受けると、専門家としての意見として合理的正しい判断だと考えがちである。ただ、彼らにも間違いはあり、考え方のクセみたいなものはある。それは、僕らも同じだ。そのことに気づくきっかけを得られたことでは、この本を読んでよかった!
- 投稿日:2023年07月29日
最近よく聞く行動経済学の、医療での話。医師と患者の間の意思疎通・意思決定の際に生じる心理について分かりやすく説明されている。命に関わる選択を迫られた時、冷静に合理的な選択を行うため、医師側と患者(あるいは家族)側の双方理解・バイアス理解が重要。また、医療において男女でリスク回避能力に統計的有意差があるというのは意外ではあったが納得感はあった。
- 投稿日:2023年07月08日
行動経済学って最近よく聞くからちょっと気になって読んでみました
図書館では経済のところにあるかと思いきや、まさかの心理学
バイアスとか、サンクコストとか、フレーミング効果とか、以前心理学を学んでいたので懐かしいと思いながら読みました
患者、医療者だけでなく、医療者からの視点もあってかなりためになりました
ただ、仕方ないと思いますがカタカナが多すぎて慣れないと時々意味がごちゃごちゃになります
説明をするとき、この本をちょっと思い出せたら
医療現場、って書いてありますが他の場所でもきっと同じようなことが起きているのだろうと思います
楽天ブックスランキング情報
-
 週間ランキング(2025年04月07日 - 2025年04月13日)
週間ランキング(2025年04月07日 - 2025年04月13日)
本:第-位( - ) > 医学・薬学・看護学・歯科学:第3285位(↑) > 基礎看護学:第383位(↑) > その他:第371位(↑)
-
 日別ランキング
日別ランキング
ランキング情報がありません。
お気に入り新着通知
- 未追加:
- 2件
ランキング:医学・薬学・看護学・歯科学
※1時間ごとに更新
-
1

-
クエスチョン・バンク 看護師国家試験問…
医療情報科学研究所
6,490円(税込)
-
2

-
女性の尿もれ・ゆるみ・臓器脱 自力で克…
奥田逸子
1,738円(税込)
-
3

-
看護師・看護学生のためのレビューブック…
岡庭 豊
6,930円(税込)
-
4

-
どんなに硬い体も柔らかくなる! 名医が…
高平尚伸
1,958円(税込)
-
5

-
今日の治療薬2025
伊豆津宏二
5,280円(税込)
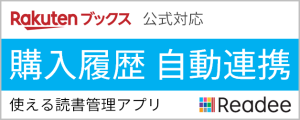



![医療現場の行動経済学すれ違う医者と患者[大竹文雄]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/5071/9784492315071.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![医療現場の行動経済学すれ違う医者と患者[大竹文雄]](https://tshop.r10s.jp/book/cabinet/5071/9784492315071.jpg)