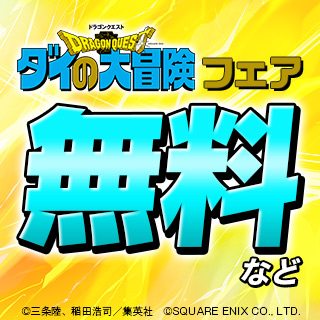商品情報

商品説明
内容紹介
日本占領下の東南アジアに、B29の大空襲を受けた東京に、原爆投下直後の広島に、そしてソ連軍が怒濤のように押し寄せる満州や樺太の地に、医師たちの姿があった。国家に総動員された彼らは、食料や医薬品が欠乏する過酷な状況下で、陸海軍将兵や民間人への医療活動を懸命に続けていた。二十年の歳月をかけ、世に送り出された、帚木蓬生のライフ・ワーク。日本医療小説大賞受賞作。
商品レビュー(17件)
- 総合評価
 4.36
4.36
楽天Koboのレビュー
まだレビューがありません。 レビューを書く
ブクログのレビュー(17件)
- 投稿日:2025年03月02日
2025/3/2読了
『花散る里の病棟』で、野北家二代、宏一医師の軍医時代のエピソードを読んで、同じく帚木蓬生作品の本作を読みたくなった。
収録された15篇は、戦時中の医師や軍医の手記を基にした創作なのだろうが、実際の体験に基づいたストーリーで、また一人称の語りであるが故に、インタビューの様に生々しい。内地や旧満州のエピソードが多かったが、特に満州では、終戦も知らされずに、撤退を続ける中で攻撃を受けたり、武装解除の後もソ連軍から理不尽な扱いを受けたり、戦争が終わったのに生き残るために闘わなくてはならないという、極限状態が描かれていた。そんな中で医療活動にあたりながらも、平時なら失われるはずのない命が失われていくのを見るしかなかった軍医たちの無力感、無念……。ほんの80年程前に起きていたことであり、今まさにウクライナやガザで同様のことが起きていると思うと、余計に心穏やかには読めなかった。 - 投稿日:2024年08月24日
*星4つ相当です
厚労省と日本医師会と新潮社が企画した日本医療小説大賞 第一回受賞作との事。
戦中戦後の軍医または軍医の卵がどのように生活したかよく分かる15編の短編からなる。
爺さんが陸軍軍医だったという人は読むと良いと思います。うちの爺さんもそうでした。
作家さんは精神科医で「ははきぎ」と読むそうで、これまで名前は見かけるも手に取ったのは初めて。圧倒的な取材力でこの高解像度はありがたい。 - 投稿日:2018年09月01日
第二次大戦で軍医として関わった人たちの短編集。
内地勤務だった人もいれば前線に近い外地での救命活動に携わった人、のんびりとした環境で終戦を迎えた人もいれば、やっとの思いで内地に帰り着いた人もいる。
そして軍医ならではなのは、やはり命を救う、病気を治すことに使命感を感じ務めを全うする姿勢だと思う。
膨大な参考資料を読み取材した上で創作した話だと思うが嘘は言っていないだろう。
15篇もあるので途中で飽きるが、読む価値はあると思う。
楽天ブックスランキング情報
-
 週間ランキング
週間ランキング
ランキング情報がありません。
-
 日別ランキング
日別ランキング
ランキング情報がありません。
-
期間限定!イチオシのキャンペーン
電子書籍のお得なキャンペーンを期間限定で開催中。お見逃しなく!
ランキング:小説・エッセイ
※1時間ごとに更新
-
1

-
 カフネ
カフネ
阿部暁子
1,870円(税込)
-
2

-
 正体
正体
染井為人
990円(税込)
-
3

-
 ポイズンドーター・ホーリーマザー
ポイズンドーター・ホーリーマザー
湊かなえ
660円(税込)
-
4

-
 そのシンデレラストーリー、謹んでご辞退…
そのシンデレラストーリー、謹んでご辞退…
Q矢
1,540円(税込)
-
5

-
 片田舎のおっさん、剣聖になる 9 ~た…
片田舎のおっさん、剣聖になる 9 ~た…
佐賀崎しげる
1,430円(税込)


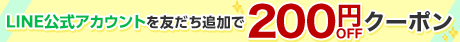
























































 電子書籍版
電子書籍版