アイデアのつくり方
- | レビューを書く
1,100円(税込)送料無料
- 発行形態:
- 紙書籍 (単行本)
この商品が関連するクーポン・キャンペーンがあります(10件)開催中のキャンペーンをもっと見る
※エントリー必要の有無や実施期間等の各種詳細条件は、必ず各説明頁でご確認ください。
- 【楽天モバイルご契約者様】条件達成で100万ポイント山分け!
- 本・雑誌全品対象!条件達成でポイント最大10倍(2025/4/1-4/30)
- 【ポイント5倍】図書カードNEXT利用でお得に読書を楽しもう♪
- 条件達成で本全品ポイント2倍!楽天ブックスの読書管理アプリを使おう
- 【楽天Kobo】初めての方!条件達成で楽天ブックス購入分がポイント20倍
- 【楽天全国スーパーx楽天ブックス】最大1000円分クーポンプレゼント!
- エントリー&お気に入り新着通知登録で300円OFFクーポン当たる!
- 楽天モバイル紹介キャンペーンの拡散で300円OFFクーポン進呈
- 【楽天24】日用品の楽天24と楽天ブックス買いまわりでクーポン★
- 【楽天マガジン】楽天ブックスでのお買い物が全品ポイント10倍に!
商品情報
- 発売日: 1988年04月08日頃
- 著者/編集: ジェームス・W・ヤング(著), 今井 茂雄(訳), 竹内 均(解説)
- 出版社: CCCメディアハウス
- 発行形態: 単行本
- ページ数: 102p
- ISBN: 9784484881041
この商品を買った人が興味のある商品
よく一緒に購入されている商品
商品説明
内容紹介
“どうやってアイデアを手に入れるか”への解答がここにある! アメリカの超ロングセラーが現代に問う先進の発想術。内容紹介(出版社より)
アイデアはどうしたら手に入るかーー
その解答がここにある!
アメリカの超ロングセラーが明かす究極の発想術。
60分で読めるけれど一生あなたを離さない本。“アイデアをどうやって手に入れるか”という質問への解答がここにある。
内容紹介(「BOOK」データベースより)
60分で読めるけれど一生あなたを離さない本。《アイデアをどうやって手に入れるか》という質問への解答がここにある。
目次(「BOOK」データベースより)
この考察をはじめたいきさつ/経験による公式/パレートの学説/心を訓練すること/既存の要素を組み合わせること/アイデアは新しい組み合わせである/心の消化過程/つねにそれを考えていること/最後の段階/2、3の追記
商品レビュー(772件)
- 総合評価
 3.95
3.95
ブックスのレビュー(60件)
-
内容が・・・。
- よっし~2000
- 投稿日:2011年01月12日
いろいろと他の本を読んでて基礎的な感覚があれば良いですが、いきなり読むと例とかが古く内容がわかりにくいです。
これなら、前に読んだ本の方がいいかなぁ~と思いました。4人が参考になったと回答
-
アイデアを生む原理と方法
- ぼん・ぼやーじゅ
- 投稿日:2009年01月10日
アイデア創出の原理と方法を説いた良書です。
本自体がとても薄いですが、その後ろ3分の1が竹内均氏の解説なので、本文は本の厚さのわずか3分の2程度。本当にアッという間に読めてしまいました。しかしその薄さの中に必要且つ十分な内容がきちんとまとめられているから素晴らしい。要は第一に原理、第二に方法であり、それぞれは以下のとおり:
★アイデア作成の原理=(1)既存の要素の新しい組み合わせである。(2)新しい組み合わせを作り出す才能は事物の関連性を見つけ出す才能により高められる。
★アイデア作成の方法(5つの段階)=(1)資料集め (2)資料の咀嚼 (3)放棄する(無意識に任せる) (4)ひらめく (5)検証する。具体化し、展開する。
竹内氏の解説も本書を価値を高めていると思う。
アイデアのバイブル的な著作である本書が広告業界のみならずどのような分野にでも当てはまる内容であることを、竹内氏の専門である自然科学分野での発見(「大陸移動説」や「種の起源」等)との共通性に照らして解説している。
また、「アイデアのつくり方」と原理的には同じという竹内氏の「私なりの方法」も素晴らしい。ひと月300枚(=1日に10枚)の原稿を二十数年も休まず書き続けていること。また、15分という時間の断片を使って作った3枚程度の原稿の断片を100くっつけることで、1冊の本を容易に作り上げてしまうこと等。最後に方法論や道具に凝って結局何もしないということのないよう「直ぐに仕事を始めよ」との言葉で、本末転倒とならぬよう戒めていることは全くそのとおりで、常に心しておかなければならないと感じました。4人が参考になったと回答
-
アイディアつくり
- ツンさん
- 投稿日:2010年02月13日
インターネットの何かの記事でこの本のことを知り、即購入しました。
---
元の記事で紹介されているとおり、短時間が読みきることができましたが、確かにエッセンスが詰まっていました。
---
内容としては、至極当たり前のことが書かれていますが、やはり何事も基本に忠実に、ということですかね。
---
こう書くと、なにかものすごい魔法のセオリーを期待した方をガッカリさせるかもしれませんが、この当たり前の方法こそが魔法のセオリーだと気付かされました。3人が参考になったと回答
ブクログのレビュー(712件)
- 投稿日:2025年03月14日
その名の通り、アイデアの作り方がスッキリとまとめられた一冊。
読むのが速い人であれば60分もかからなさそう。
アイデアを作る上での3・4の過程は、アイデアが生まれる「3B」を想起させた。確かにあれこれ考えてどうにかアイデア(や解法など)を捻り出そうとしている時よりも、「わからんから一旦後回し!」ってして別のことしてたり、そのことなんて完全に頭にないようなリラックスしている時の方が、ふと「あぁこれだ!」って閃くことが多いなと思う。アイデアに限らず考え事とかも、そのことを考えなくなった期間を経て、納得できたりいつのまにか整理されてたりするなぁとも思う。
また、この本の中で個人的に印象に残った表現がいくつかある。
「南太平洋の海に突然島が出現するという物語に、架空小説が付与しているあの神秘性」
「言語=シンボル」
「良いアイデアというのはいってみれば自分で成長する性質を持っている」
「心ここにあらざれば、見れども見えず、聞こえども聞こえず」
「美的直観」
「〈詩と散文〉〈舞踊と歩行〉」
などである。
サクッと読めるし、内容のまとめもわかりやすいし、とても良い読書だったと思う。 - 投稿日:2025年03月04日
しないことリストでオススメしていたので選びました。
読書初心者には訳が少し難しかったけど、短くてスラスラ読めた。アイデア作りの手順がわかりやすくて、どこかで実践してみたいと思った。パレートの法則が印象的で、やりたいことの100%を中途半端に進めるよりも、全体の20%のことを全力で進めることの方が大切だと思いました。 - 投稿日:2025年02月24日
アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ
翻訳のため、若干読みにくさありって感じ
解説にも良いことが書かれていると思う
①資料集め(意識的にすること)
→ インプットの量を多くする
何かテーマがある場合はそれに関連する
情報を集めてカードに1つずつ書いていく
②集めた資料を咀嚼する(意識的にすること)
→ ①で集めた資料の内容や意味についてよく考えてみる
カードに1つずつ書いてる場合は2つのカードを見比べてみてどうしたらその事実が噛み合うかや共通点を探したりする
③一旦考えることから離れる(無意識の段階)
→ サウナ行ったり散歩したり風呂入ったり
考えることから離れることで急にアイデアが湧いてきたりする
閃いたアイデアはすぐに使えそうなことではなくても書き留めておく
④閃きの段階(無意識の段階)
⑤アイデアを具体化して展開させる(意識的にすること)
→ 閃いたアイデアを自分の中でとどめない
行動にうつす、言葉にする
お気に入り新着通知
- 未追加:
- 3件
ランキング:人文・思想・社会
※1時間ごとに更新
-
1

-
ポケット六法 令和7年版
荒木 尚志
2,420円(税込)
-
2

-
【入荷予約】「賢い子」の親が本当にやっ…
講談社
1,459円(税込)
-
3

-
DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる…
ビル・パーキンス
1,870円(税込)
-
4

-
科学的根拠(エビデンス)で子育て
中室牧子
1,980円(税込)
-
5

-
小学教科書ワーク 社会 5年 東京書籍版
1,518円(税込)
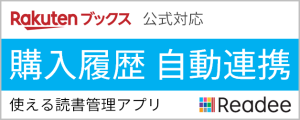


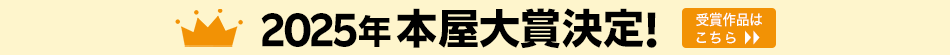

















![影響力の武器[第三版]](http://tshop.r10s.jp/book/cabinet/4220/9784414304220_1_3.jpg?fitin=160:230&composite-to=0,*|160:230)












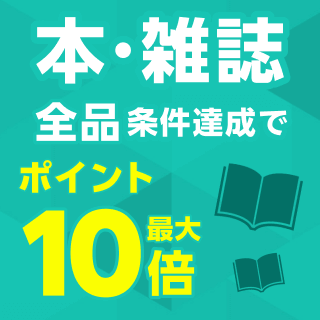

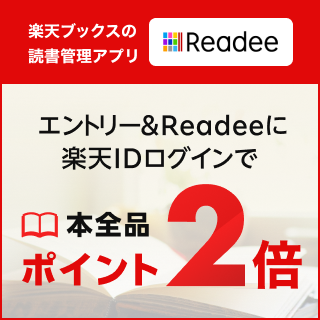




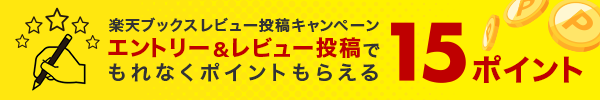








![アンガーマネジメント超入門 「怒り」が消える心のトレーニング [図解] (特装版)](http://tshop.r10s.jp/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9387/2000010299387.jpg?downsize=80:*)







