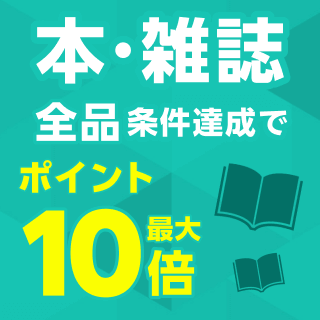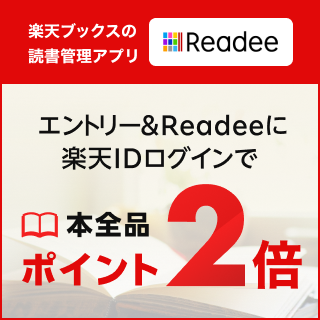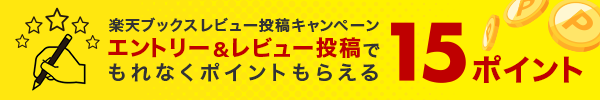なぜ私たちは燃え尽きてしまうのか
- | レビューを書く
2,420円(税込)送料無料
- 発行形態:
- 紙書籍 (単行本)
この商品が関連するクーポン・キャンペーンがあります(10件)開催中のキャンペーンをもっと見る
※エントリー必要の有無や実施期間等の各種詳細条件は、必ず各説明頁でご確認ください。
- 【ポイント5倍】図書カードNEXT利用でお得に読書を楽しもう♪
- 【楽天ブックス×楽天ウェブ検索】条件達成で10万ポイント山分け!
- 本・雑誌全品対象!条件達成でポイント最大10倍(2025/3/1-3/31)
- 【対象者限定】全ジャンル対象!ポイント3倍 おかえりキャンペーン
- 【楽天モバイルご契約者様】条件達成で100万ポイント山分け!
- 条件達成で本全品ポイント2倍!楽天ブックスの読書管理アプリを使おう
- 【楽天ブックス×楽天ラクマ】条件達成で10万ポイント山分け!
- エントリー&お気に入り新着通知登録で300円OFFクーポン当たる!
- 楽天モバイル紹介キャンペーンの拡散で300円OFFクーポン進呈
- 【楽天24】日用品の楽天24と楽天ブックス買いまわりでクーポン★
商品情報
- 発売日: 2023年10月27日
- 著者/編集: ジョナサン・マレシック(著), 吉嶺英美(訳)
- 出版社: 青土社
- 発行形態: 単行本
- ページ数: 360p
- ISBN: 9784791775910
この商品を買った人が興味のある商品
よく一緒に購入されている商品
商品説明
内容紹介(出版社より)
バーンアウト文化への処方箋
「燃え尽き(バーンアウト)症候群」は仕事への不満やストレスを語るときの用語として流通しているが、その意味は正確に理解されておらず、激務の疲労や仕事への絶望に苦しむ労働者の役に立っていない。本書は、大学教授の仕事に燃え尽き、寿司職人やコインパーク管理人として生計を立てていた異色の経歴を持つ著者が、なぜ過酷な仕事に高い理想を持つのかを歴史的・心理学的に分析し、燃え尽きを解決できた個人やコミュニティーを明らかにする。
内容紹介(「BOOK」データベースより)
「燃え尽き症候群」はストレスや仕事への不満を語るときの言葉として流通しているが、その意味は正確に定義されておらず、激務の疲労や仕事に絶望した労働者の役には立っていない。本書は「ノーを言えるようになる」ことや「瞑想する」ことの無意味性を明らかにしながら、仕事が今や私たちの価値観とアイデンティティを象徴するものになってしまっていることを指摘し、そこから逃れるための道を提示する。燃え尽きて大学教授の職を辞すことになった著者によるバーンアウト文化への処方箋。
目次(「BOOK」データベースより)
第1部 バーンアウト文化(誰もがバーンアウトしているのに、誰もバーンアウトの実態を知らない/バーンアウトー最初の二〇〇〇年/バーンアウト・スペクトラム/バーンアウトの時代、労働環境はいかに悪化したか/仕事の聖人と仕事の殉教者ー私たちの理想の問題点)/第2部 カウンターカルチャー(すべてを手に入れることはできるー新たな「良い人生」像/ベネディクト会は仕事という悪霊をどのように手なづけたのか/さまざまなバーンアウト対策)/終わりに ポスト・パンデミックの世界における非エッセンシャルワーク
著者情報(「BOOK」データベースより)
マレシック,ジョナサン(Malesic,Jonathan)
エッセイスト、ジャーナリスト。大学教授の職を燃え尽き症候群で失った経験を、自らの専門でもある神学などの視点から分析を続ける
吉嶺英美(ヨシミネヒデミ)
翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
商品レビュー(11件)
- 総合評価
 3.80
3.80
ブックスのレビュー
まだレビューがありません。 レビューを書く
ブクログのレビュー(11件)
- 投稿日:2024年12月20日
現代の仕事が工場労働的な作業中心ではなく、サービス業的な対人の仕事が増え、仕事に意欲などの感情が求められるようになってきたという分析には衝撃を受けた。
さらに、給与や裁量権は増えず仕事の環境は悪化しているとも指摘されていた。
一方で仕事が、良い人格、尊厳、人生の目的を与えてくれるという期待は増すばかりだという分析もあり、自分の実体験も踏まえて腑に落ちた。
このような理想と現実のギャップによって人々はバーンアウトしてしまうという。
このような「高貴な嘘」を再編して、より良い社会を構成しようというのが著者の目的なのはわかる。
ただ、労働至上主義的な「高貴な嘘」が無くなっても別の「高貴な嘘」が作られて同じようなことになるだけなのかなと思った。
もちろん、バランスを考え、今より良い嘘にすればいいと考えるかもしれない。
それは確かにそうだと思うが、労働至上主義も生まれや貴族主義のような価値観へのカウンターだったんじゃないかという気もしてくる。
全ての人に尊厳を与えるというのも難しそうだ。
あなたを認めますと言われれば確かに嬉しいが、皆がそうするなら普通のことになってしまうのではないかと思った。
また、人にも仕事にも人気や不人気がある。
これは尊厳と密接に関係してそうだし、相当根が深い話のように思える。 - 投稿日:2024年12月01日
私には必要な本だった。
「勤労が美徳」なんていう価値観は、資本主義や為政者が労働を搾取するために打ち出したもの。働いて稼ぐという行為は、自らの時間を収益化するために、その関係性や制約において、少なからず不愉快なもの、と諦めていた。しかし、美徳に反してそう考えてみる事はストレスでもあった。まして行動を起こすには罪の意識さえある。
マルクスならこれを人間的な疎外と表現するだろうか。つまり、この本でも取り上げられる「脱人格化」の事だ。教育機関は職業訓練校の機能を果たし、生まれながらに上流ではない階層や、途上国や敗戦国は大方この仕組みに組み込まれ、日々、精神も肉体もすり減らし、同じ労働者との僅かな余暇に健全性と勤労の清々しさを味わった気分になり、ひたすら名誉奴隷を目指すのだ。
ー 働けばかならず幸せになるという約束は、ほぼまやかしだ。それは哲学者のプラトンが「高貴な嘘」と呼ぶもので、社会の基本的な仕組みを正当化する一種の虚構にほかならない。けれどもしその嘘を人々が借じなかったら、社会は大混乱に陥るとプラトンは説いている。そしてこの高貴な嘘は私たちに、勤勉に働くことには価値があると思い込ませる。たとえ上司のために働いているだけでも、自分は最高善を行っていると思い込ませるのだ。
この〝気付き“の果てに、バーンアウトは存在する。我々が会社と呼び、仲間意識を醸成して忠義を感じたり、社会貢献していると信じた集合体は、隠しもせず、株主のものだと教えられる。しかし、株主からは働くあなたは見えず、会社は株主を見るから、あなたが心を砕き、自ら我慢を強いて、家族を犠牲にして生きていく人生は、報われない。気まぐれで偶発的な名誉奴隷の判断で、面接され査定され辞令を下される運命にある。
ー たとえどんなに頑張っても、得られる報酬は変わりそうになかったからだ。いまとなっては、あのころ大学にあんなに気を遣う必要などなかったと思うことさえある。もっと手を抜いても、かまわなかったのだ。一世紀以上前のことだが、ドイツの社会学者、マックス・ヴェーバーは、野心に燃える若き大学数授たちに「きみは毎年、毎年、凡庸なやつらが自分を飛び越して昇進していく状況に対して、憤慨もせず、ひがみもせずに耐えられると思うかね?」とつねづね尋ねていたというが、私は彼の言葉に妙な慰めを覚える。ほかの多くの業界でもそうだろうが、学者の世界も不公平なことは頻繁に起こる。成果主義を装ってはいるが、長年の積み重ねが不運によって一瞬でなかったことになることも多いのだ。
資本主義がどうなろうかと関心を持つが、最も気にしておくべきは、それが我々の労働にどのような影響を持つかだ。気力も体力も吸い尽くされ、人生の晩年に釈放されても、あなたの青春は取り戻せない。健康寿命の分だけ生きられたとしても、鏡に映るのは、老けた労働者。何かしらの病や常備薬の必要な生活、痛みを抱えた足腰、鈍った頭、つまり労働価値を失った存在だ。
ー 政治哲学者のカティ・ウィークスの言葉を借りれば、いまや上司は労働者の「態度、やる気、行動に基づいて」採用し、評価し、昇進させ、解雇することができるのだ。つまり従業員の感情は売買可能であり、シフトのあいだ雇用主は彼らからその感情を借り受け、変容させているのだ。
ー だが皮肉なことに、勤勉に働くことで良い人生が手に入るという理想を言じること自体が、良い人生を手に入れる際の最大の障害になるのだ。
残念なことに、起業家も経営者も、こうした呪縛からは解き放たれない。洗脳された幸福の中で死を迎えられるなら怖くはない。しかし、自ら洗脳を解こうとする人間は、取り返しがつかない。読書を重ねて考え続ける事は、その立ち位置を中途半端にする意味では自殺行為であり、罪深い。
社会的な進化や成長なんて本当に必要だろうか。持続のためにゆっくりと衰退軌道に入る時、蓄積されたグリードは何を吐き出し始めるのか。
我慢せずに生き始めなければ。 - 投稿日:2024年11月23日
人間の価値と雇用されているか否かは別ですと。まぁそりゃそうだ。仕事と人生の大事な事を切り離しましょう的な話だが、仕事に打ち込まないと人類の進歩も頓挫しちゃいますよ。まぁそれは80:20の法則で優秀な20%の人がやればいいのか。適材適所で放っておいても自然とそうなっていくのか。どうでもいい仕事はロボットに任せたらいいというような結論だが、そのロボットは誰かの仕事で創られている。出家した僧侶の様にお経を唱えているだけでは世の中は進化しない。。
お気に入り新着通知
- 未追加:
- 2件
ランキング:人文・思想・社会
※1時間ごとに更新
-
1

-
ほどよく孤独に生きてみる
藤井 英子
1,540円(税込)
-
2

-
つば九郎のぽじてぃぶじんせいそうだん。
つば九郎
1,100円(税込)
-
3

-
スクールプランニングノート2025年度版A…
スクールプランニングノート制作委員会
2,310円(税込)
-
4

-
伊勢白山道事典 第2巻
伊勢白山道
2,970円(税込)
-
5

-
人生の経営戦略
山口 周
1,980円(税込)
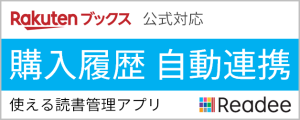



![なぜ私たちは燃え尽きてしまうのか[ジョナサン・マレシック]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/5910/9784791775910_1_3.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![なぜ私たちは燃え尽きてしまうのか[ジョナサン・マレシック]](https://tshop.r10s.jp/book/cabinet/5910/9784791775910_1_3.jpg)