ヒトはなぜ死ぬ運命にあるのかー生物の死 4つの仮説ー(新潮選書) (新潮選書) [電子書籍版]
更科功
- | レビューを書く
1,650円(税込)
- 電子書籍 (楽天Kobo)
- ヒトはなぜ死ぬ運命にあるのかー生物の死 4つの仮説ー(新潮選書)
- 1,650円
- 紙書籍 (全集・双書)
- ヒトはなぜ死ぬ運命にあるのか
- 1,650円
この商品が関連するクーポン・キャンペーンがあります(1件)開催中のキャンペーンをもっと見る
※エントリー必要の有無や実施期間等の各種詳細条件は、必ず各説明頁でご確認ください。
商品情報
この商品を買った人が興味のある商品
商品説明
内容紹介
約40億年前に誕生した初期の生物に、寿命はなかった。にもかかわらず、死ぬことは必要だったーー生物は進化し、多様性を生み出し、複雑な構造となったからだ。生物は生き残るため、寿命を得たのである。「死」に関する4つの仮説の歴史的な盛衰を通して、生物の「寿命」がどのように生まれたのかをひもといていく。
商品レビュー(6件)
- 総合評価
 3.83
3.83
楽天Koboのレビュー
まだレビューがありません。 レビューを書く
ブクログのレビュー(6件)
- 投稿日:2024年09月02日
後半、遺伝の確率や遺伝子、エピジェネティクスの話が出てきて、うーん難しい…というところがあったけれど
生物にとっての死がどのようにおこるのか
少しだけ理解できて楽しめた。
おばあさん仮説と閉経の話、
著者は相関があるかどうか明言していないが
有ったら面白い。
あるなら、うちの母にももう少し
孫育てを頑張ってほしいところだが。
おばあさん仮説、面白いのでぜひ読んでほしい - 投稿日:2024年06月01日
2023/09/06 読み終わった
コテンラジオの老いと死の回で紹介されていたので。あとは、深井さんがおすすめしていた同じ著者の「進化論はいかに進化したのか」が面白かったので。
なぜヒトには寿命があるのか、究極の答えは自然淘汰の結果だということ。つまり、そういう風に進化したから。だそうだ。
歴史的にさまざまな説が提唱されてきた:
- 体が大きい方が寿命が長い
- 代謝が少ない方が寿命が長い
- 次の世代に譲るため←循環論法
最近の説は20世紀後半のものも。でもそれも否定されている。
結局、自然淘汰で全部説明できる。これはきれいだと思った。
因果関係を間違えて認識していないかを常に意識するという観点も面白かった。我々は太陽がないと生きていけないが、太陽は我々を生かすために輝いているのではない。
そもそも、生き物が絶対に死ぬっていう当たり前(と思っている)ことも、本当は当たり前じゃない。これも新しい視点。 - 投稿日:2023年07月13日
第1章は難しかったけれど種の保存説からとても楽しかった。
何故産むことができなくなっても長く生きるのかという疑問から人間は一人で育てるのは難しいから育てるために長生きしている説はすごく腑に落ちた。
自然淘汰の話は常に興味深く楽しく読めたこれだけで本一冊読みたい。
これから先人間がどうなっていくのか楽しみ。見届けられないのがとても残念
-
期間限定!イチオシのキャンペーン
電子書籍のお得なキャンペーンを期間限定で開催中。お見逃しなく!
ランキング:科学・医学・技術
※1時間ごとに更新
-
1

-
 僕には鳥の言葉がわかる
僕には鳥の言葉がわかる
鈴木俊貴
1,683円(税込)
-
2

-
 売れる組織 売れる営業
売れる組織 売れる営業
田中大貴
2,200円(税込)
-
3

-
 疲労とはなにか すべてはウイルスが知っ…
疲労とはなにか すべてはウイルスが知っ…
近藤一博
1,100円(税込)
-
4

-
 人を動かす 改訂文庫版
人を動かす 改訂文庫版
D・カーネギー
880円(税込)
-
5

-
 はじめての3DモデリングBlender 4 超入門…
はじめての3DモデリングBlender 4 超入門…
富元秀俊
3,499円(税込)


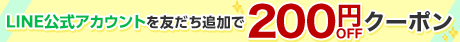











































 電子書籍版
電子書籍版

















