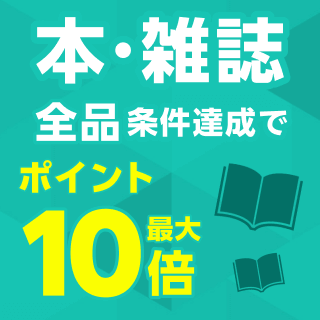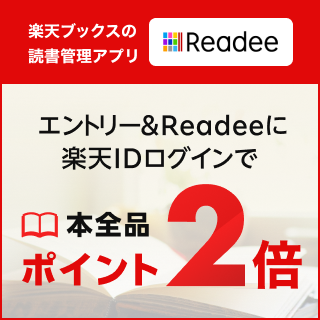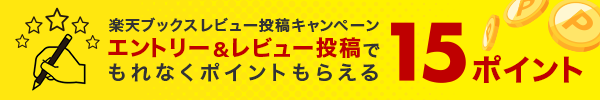- 現在地
- トップ > 本 > 人文・思想・社会 > 雑学・出版・ジャーナリズム > その他
スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長が教える 脳が一生忘れないインプット術
- | レビューを書く
1,650円(税込)送料無料

この商品が関連するクーポン・キャンペーンがあります(10件)開催中のキャンペーンをもっと見る
※エントリー必要の有無や実施期間等の各種詳細条件は、必ず各説明頁でご確認ください。
- 【楽天モバイルご契約者様】条件達成で100万ポイント山分け!
- 本・雑誌全品対象!条件達成でポイント最大10倍(2025/4/1-4/30)
- 【ポイント5倍】図書カードNEXT利用でお得に読書を楽しもう♪
- 条件達成で本全品ポイント2倍!楽天ブックスの読書管理アプリを使おう
- 条件達成でポイント2倍!楽天モバイルご契約者様はさらに+1倍
- 【楽天Kobo】初めての方!条件達成で楽天ブックス購入分がポイント20倍
- 【楽天ブックス×楽天ウェブ検索】条件達成で10万ポイント山分け!
- 【楽天全国スーパーx楽天ブックス】最大1000円分クーポンプレゼント!
- エントリー&お気に入り新着通知登録で300円OFFクーポン当たる!
- 楽天モバイル紹介キャンペーンの拡散で300円OFFクーポン進呈

商品説明
内容紹介(出版社より)
TBS系列 王様のブランチで紹介され大反響!!
大量の情報があふれている現代において、
「必要な情報をできるだけ早く、効果的に頭に叩き込みたい」と考える人は多いでしょう。
しかし、せっかく学んだことをすぐに忘れてしまったり、覚えたはずなのに身についていなかったり、なかなか実践できないという人も多くいます。
そんな人のために、スタンフォード大学・オンラインスクール校長が、脳科学と心理学に基づく効果的なインプット方法について紹介します。
インプットに関する情報はたくさんあふれていますが、その中には科学的根拠がないものも。
本書では、最新の脳科学と心理学に裏打ちされた方法の中で、特に効果が高くて、すぐにでも実践できるものを厳選して解説しています。
(以下、「はじめに」より)
例えば、次のインプット法のリストをご覧ください。
・本を読むときは「つまみ読み」から始める
・記憶を定着させるためには繰り返し読み直す
・YouTube動画で学ぶときは字幕付きで見る
・ポッドキャストは1.5倍速までがおすすめ
・メモやノートは手書きでとる
・始める前に前回学んだことを思い出す
どれも多くの人たちが実践している日常的なインプット法です。
しかし、後ほどお話しするように、これら6つの学び方のうち、科学が明かした正解はたったの3つ。
他は、思ったほどの効果が確認されていません。
この本では他にもたくさんのインプット方法を科学的に吟味して、脳や心のメカニズムを最大限に生かしたインプット法をわかりやすく説明していきます。
■ ■ ■ もくじ ■ ■ ■
第1章 脳はどうやってインプットしているのか?
第2章 脳を最大限にエンゲージする「読むインプット」術
第3章 現代を生き抜く力! マルチメディアでの学習法
第4章 脳に焼きつく記憶メソッド
第5章 インプットの質を上げるモチベーション管理
第6章 スタンフォード式 AI時代の情報の見分け方
■ ■ ■ 著者プロフィール ■ ■ ■
星友啓(ほし・ともひろ)
スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長/哲学博士/EdTechコンサルタント
1977年東京生まれ。
東京大学文学部思想文化学科哲学専修課程卒業。
その後渡米し、Texas A&M大学哲学修士、スタンフォード大学哲学博士課程修了。
同大学哲学部講師として論理学で教鞭をとりながら、スタンフォード・オンラインハイスクールスタートアップ プロジェクトに参加。2016年より校長に就任。
現職の傍ら、哲学、論理学、リーダーシップの講義活動や、米国、アジアにむけて、教育及び教育関連テクノロジー(EdTech)のコン サルティングにも取り組む。
著書に『スタンフォード式生き抜く力』(ダイヤモンド社)、『脳科学が明かした!結果が 出る最強の勉強法』(光文社)、『全米トップ校が教える自己肯定感の育て方』『脳を活かす スマホ術』(いずれも朝日新聞出版)、『スタンフォード・オンラインハイスクール校長が教え る子どもの「考える力を伸ばす」教科書』(大和書房)、『スタンフォードが中高生に教えてい ること』『「ダメ子育て」を科学が変える!全米トップ校が親に教える57のこと』(いずれも SBクリエイティブ)がある。
内容紹介(「BOOK」データベースより)
一生使えるインプット法で質と効率が上がる!
目次(「BOOK」データベースより)
第1章 脳はどうやってインプットしているのか?/第2章 脳を最大限にエンゲージする「読むインプット」術/第3章 現代を生き抜く力!マルチメディアでの学習法/第4章 脳に焼きつく記憶メソッド/第5章 インプットの質を上げるモチベーション管理/第6章 スタンフォード式 AI時代の情報の見分け方
著者情報(「BOOK」データベースより)
星友啓(ホシトモヒロ)
スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長/哲学博士/EdTechコンサルタント。1977年東京生まれ。東京大学文学部思想文化学科哲学専修課程卒業。その後渡米し、Texas A&M大学哲学修士、スタンフォード大学哲学博士課程修了。同大学哲学部講師として論理学で教鞭をとりながら、スタンフォード・オンラインハイスクールスタートアッププロジェクトに参加。2016年より校長に就任。現職の傍ら、哲学、論理学、リーダーシップの講義活動や、米国、アジアにむけて、教育及び教育関連のテクノロジー(EdTech)のコンサルティングにも取り組む(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
商品レビュー(14件)
- 総合評価
 3.54
3.54
ブックスのレビュー
まだレビューがありません。 レビューを書く
ブクログのレビュー(14件)
- 投稿日:2025年03月03日
脳のインプット術や速読インプットの科学的解明、アクティブリーディング、ワーキングメモリーの限界、リトリーバル効果、ハイライトの効果、などなど。
脳が情報をどのようにインプットするかを理解し、効果的な学習法を実践することので効率の良いインプット術が学べる。
読書は目で読むものではなく、脳の理解が重要で、実は読書中の8割は文字を見ていないことが分かっている。
脳のインプット術は、情報を視覚的に捉えるだけでなく、脳がその意味を理解するプロセスを重視し、アクティブリーディングを通じて、情報に能動的に関与し、目的に合った質の高いインプットを実現する方法。
読む前にタイトルや見出しを確認し、全体の内容を把握することで、効率的なインプットが可能になる。さらに、読みながらメモを取ることで、情報の理解と記憶の定着を促進する。メモは記録ではなく、記憶のために取る。
また、一定時間集中して学習し、集中力を維持するために休憩をこまめに入れることも大切。
最も大事な要点は「リトリーバル効果」であり。
学んだことを思い出すことで記憶を強化する学習方法。記憶力アップに最も効果的とされる。
インプットした内容を学習中、学習後、さらに定期的に思い出す習慣をつけることにより、長期記憶の定着を促進し、学習効果を高めます。
私自身この方法を実践し、脳にインプットさせて知識としての引き出しを確保して行こうと思います。
また、学生さんや試験勉強におすすめです。 - 投稿日:2025年02月19日
【学んだこと】
・インプットした内容を思い返す際、いきなり"答え"を見るのではなく、自分の頭の中だけで思い起こすことを「リドリーバル」と呼び、これは100年以上にわたる研究の積み重ねにより見出された、"学習効果の高い"インプット術である。本書では、脳内で何が起こっているかについて詳述されていないが、リトリーバルをすることによって、目的の情報を構成しているニューロンに再び電気が走る。これが繰り返されるたびに、電気の通り(思い起こすまでの時間)が速くなる。さらに、元々のニューロンに加え、リトリーバルを実践している時の場所、匂い、音楽なども新たな情報として結びつけられる。より多くの情報と関連づけられることにより、さらに思いますきっかけが増えるのである。
・「読書時間」の8割は、脳が言葉の意味を理解しているのに費やしている。これはつまり、眼球運動による速読を極めても、読書時間はその2割内でしか速めることができないということを示している。
・"聴く"と"読む"とでは、司る脳の部位が異なるが、共通する部分も大きい。すなわち、聴くにしろ読むにしろ、その質は基盤となる国語力に一定程度依存している。
・動画によるインプットをする場合、インプットの質が落ちない再生速度は1.4倍までである。1.25倍ならより最適化される場合もあり、どれだけ速くしたとしても、その限度は1.5倍程度にしておくべきだろう。
・モチベーション(動機づけ)の構成要素は、⑴関係性(人や社会との繋がり)、⑵自己効力感(自分には〇〇ができるという感覚)、⑶自立性(自分で決めたことを、自分の意思でしているという感覚)である。すなわち、何かをしたい、あるいは何かをさせたいと思っているのであれば、この3つの要素を満たすことが継続の秘訣である。 - 投稿日:2025年01月26日
十分に脳に知識を定着させたい時に、速読は科学的に不可能だと。目が何を見て理解しているのかも実証結果から語られていて良い。
速読への憧れみたいなものはあったがどうもしっくりこなく、理由が分かって良かった。じっくり行ったり来たりして定着させるようにする。元々そういったやり方だったし。
最初にメタ認知が重要となっていて、要は知らない事を知る、無知の知が必要と。後は方法論。動画、音、読書どれがどんなメリットがあるのか脳科学も絡めて書いてあって説得力がある。
楽天ブックスランキング情報
-
 週間ランキング(2025年03月24日 - 2025年03月30日)
週間ランキング(2025年03月24日 - 2025年03月30日)
本:第-位( - ) > 人文・思想・社会:第3285位(↓) > 雑学・出版・ジャーナリズム:第43位(↓) > その他:第25位(↓)
-
 日別ランキング
日別ランキング
ランキング情報がありません。
お気に入り新着通知
- 未追加:
- 星友啓
ランキング:人文・思想・社会
※1時間ごとに更新
-
1

-
【入荷予約】吉本ばななが友だちの悩みに…
吉本ばなな
660円(税込)
-
2

-
【入荷予約】となりの小さいおじさん
瀬知 洋司
1,760円(税込)
-
3

-
「賢い子」の親が本当にやっていること …
講談社
1,459円(税込)
-
4

-
【入荷予約】ほどよく孤独に生きてみる
藤井 英子
1,540円(税込)
-
5

-
【入荷予約】17歳のときに知りたかった受…
びーやま
1,650円(税込)
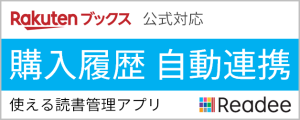



![スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長が教える脳が一生忘れないインプット術[星友啓]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/6852/9784866676852_1_2.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長が教える脳が一生忘れないインプット術[星友啓]](https://tshop.r10s.jp/book/cabinet/6852/9784866676852_1_2.jpg)