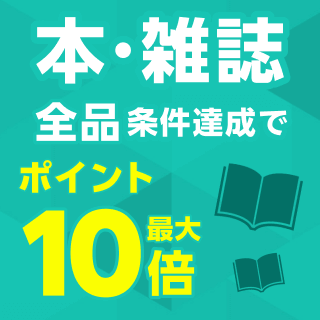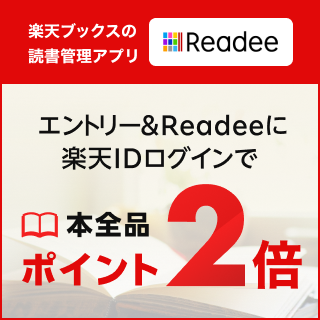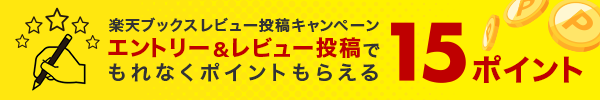去られるためにそこにいる 子育てに悩む親との心理臨床
- | レビューを書く
1,870円(税込)送料無料
- 発行形態:
- 紙書籍 (単行本)
この商品が関連するクーポン・キャンペーンがあります(10件)開催中のキャンペーンをもっと見る
※エントリー必要の有無や実施期間等の各種詳細条件は、必ず各説明頁でご確認ください。
- お買い物マラソン☆条件達成でポイント2倍!
- 【楽天モバイルご契約者様】条件達成で100万ポイント山分け!
- 本・雑誌全品対象!条件達成でポイント最大10倍(2025/4/1-4/30)
- 【ポイント5倍】図書カードNEXT利用でお得に読書を楽しもう♪
- 条件達成で本全品ポイント2倍!楽天ブックスの読書管理アプリを使おう
- 【楽天Kobo】初めての方!条件達成で楽天ブックス購入分がポイント20倍
- 【楽天全国スーパーx楽天ブックス】最大1000円分クーポンプレゼント!
- エントリー&お気に入り新着通知登録で300円OFFクーポン当たる!
- 楽天モバイル紹介キャンペーンの拡散で300円OFFクーポン進呈
- 【楽天24】日用品の楽天24と楽天ブックス買いまわりでクーポン★
この商品を買った人が興味のある商品
よく一緒に購入されている商品
商品説明
内容紹介(出版社より)
子どもの「問題」には必ず大切な意味がある。カウンセリングの事例から見えてくる親の役割や子どもへの接し方をやさしく伝える。
親の言うことを聞かない。困ったクセが直らない。学校に行かない……。子どもの「問題」には、必ず大切な意味がある。親はそのことをこころに留めて、やがて巣立っていく子どもを、どっしりとした構えで見守りたい。「子どもに去られるためにそこにいる」親の役割、それを支える心理的援助の実際を、多くの事例に基づいてやさしく伝える。
1 「症状」「問題」をもつ力
1 お化けに会いたい
2 ちょっとひと休みーー病気や問題行動のメッセージ
3 SOSを出す方向
4 子どもが言うことを聞かないーー反発することのよいところ
2 親と子の出会いと別れ
5 怒りの妖精とよばれて
6 靴をそろえる話
7 去られるためにそこにいる
8 カウンセラーも悩む親ーー巣立っていく子どもを見送る
9 甘えることをやり直すーー「退行」「甘え」の大切な意味
3 学校に行かない、ひきこもる子どもと向き合う
10 不登校の子どもに、親が家庭できること
11 家族はゆっくり変化する
12 働くことがつらくなるーー仕事を休んだ子どもと、親の役割
13 カウンセリングが「役に立つ」ということ
内容紹介(「BOOK」データベースより)
子どもの「問題」には、必ず大切な意味がある。親の言うことを聞かない。困ったクセが直らない。学校に行かない…。いつしか巣立っていく子どもに、親ができること。
目次(「BOOK」データベースより)
1 「症状」「問題」をもつ力(お化けに会いたい/ちょっとひと休みー病気や問題行動のメッセージ/SOSを出す方向/子どもが言うことを聞かないー反発することのよいところ)/2 親と子の出会いと別れ(怒りの妖精とよばれて/靴をそろえる話/去られるためにそこにいる/カウンセラーも悩む親ー巣立っていく子どもを見送る/甘えることをやり直すー「甘え」「退行」の大切な意味)/3 学校に行かない、ひきこもる子どもと向き合う(不登校の子どもに、親が家庭でできること/家族はゆっくり変化する/働くことがつらくなるー仕事を休んだ子どもと、親の役割/カウンセリングが「役に立つ」ということ)
著者情報(「BOOK」データベースより)
田中茂樹(タナカシゲキ)
1965年生まれ。徳島市で育つ。京都大学医学部卒業、同大学院文学研究科博士後期課程(心理学専攻)修了。文学博士(心理学)。医師、臨床心理士。仁愛大学人間学部心理学科教授、同大学附属心理臨床センター主任を経て、現在、佐保川診療所(奈良県)にて地域医療、カウンセリングに従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
商品レビュー(23件)
- 総合評価
 4.69
4.69
ブックスのレビュー(1件)
-
子育てとは?
- panna_238
- 投稿日:2022年04月28日
図書館で借りて読んでましたが、手元に置いてしっかり読み込みたくて買いました。
子育ては、気をつけないと子どもを私物化して自分の分身のように扱ってしまうこともありますが、そうではなく彼らが独り立ち出来るまで、それをサポートすることだと改めて考える機会になります。
子育てをされる方には一度読んでみてもらいたいな、と思います。0人が参考になったと回答
ブクログのレビュー(22件)
- 投稿日:2025年01月20日
引用(一部省略)
・しんどい状況での望ましい表現の方向
周囲に当たり散らすのか、
自分の体を使ってSOSを出すのか、
内にこもるのか。
人生を通してかなり有効なのは、
SOSを言葉で伝えること、
信頼できる相手に「自分はしんどい」と言えること。
それは幸せになるためのスキルである。
・子どもに怒ってしまう「怒りの妖精」
小言をできるだけ控える。
家で子どもがリラックスできること、
そして親もリラックスできること、
それを一番大事な目標にしてみましょう。
まず一カ月の間は怒ること、
小言を言うことをやめるように頑張る、と決心する。
ー実践省略ー
怒りの妖精は、子どもたちの支えもあって
離れていくようだった。
子どもたちは怒りの妖精をただ嫌っているので
はないのだなぁ、大好きなお母さんをずっと
守ってきてくれた怒りの妖精に対して、
子どもたちはどこかでリスペクトでもというべき
思いをもっているかのようだった。
・置き換えの問題点
「早く寝なさい」「規律」など
そこだけに注目してしまう大人は、
一時的に不安から逃れるが、
本当の問題に向き合うことが置き去りになっている。
その話題になぜそこまで感情が入り込んでくるのか。
過去の経験の本当は淋しかった自分の感情を、
怒りで押し隠していないか。
その時、子どもには何が身につき、何を失うのか。
子どもの生きる力を育てる上で、大切なことなにか。
大人の大切な姿勢は?
自分の弱さ、相手に甘えたい部分を
本当に正直に伝えること。
強い支え、頑張りをみまもり、応援、
へこたれて戻ってくれば、いつで優しく受け入れる。
そのような言葉・心の姿は、
この先の人生においての安心、
子どもを支えるメッセージになる。
もしも必要な時は、頼れると子どもに
思ってもらうこと、親の役割はその程度でいい、
大人として躾や教育的なことが浮かんでも
(浮かぶの当然、それは頑張って置いておく)
幼い子どものこころを意識しながら向き合う。
自分を見守る親、大人を背中に感じながら、
少しずつ、自立していく。
そうして親から離れていく。
子どもが安心して去っていくのを邪魔しない、
子どもからしっか離距離をとる覚悟をし
子どもと向き合う。
相手の言動で傷ついたときに、怒りで反応する
のではなく、正直に自分の痛みを相手伝えることで、
共感を得られたり、関係を悪化させることを回避したり、
そのような振る舞いのモデルを示せる。
弱さを見せる強さ、勇気を、子どもに身をもって
示すことができる。
「健常な子どもたちは親(大人)の感じる
こうした痛みを歓迎する」と言うファーマンの言葉には、
子どものもっている成長を志す強さへの確信がある。
大人の怒りの言葉を聴いていると、
自分や自分の信念ではなく、自分の親を
守ろうとしているのではないか、
と感じられることある。
親の教えを守ろうとしているのではい。
親そのものを守らなければ、と強く感じている。
そして親を攻撃しようとする相手に対して
怒っているようなのだ。
子育てにおいて、
強い不安をもっていた親(大人)が、
その不安を置き換えて子どもに接した。
子どもは、その大人が正しいと思う言動を
表面的なことだけでなく、親のこころの底の不安も
受け取ったのかもしれない。そこで子どもが親の言う
通りにしたのは、傷つきやすい不安な親を守りたい
という、親への気遣い、いたわりであったろうか。
子どもの健気な決心だっただろうか。
そして、子どもは親となり、自分が受け継いだ
親の不安を、今度は自分の子どもに押しつける。
不安の連鎖である。
・不登校について
親が「正しく」接してきたからこそ
子どもは早くに不登校になれた、S0Sを周囲に
発することができた、子どもの勇気ある行動、
自分でこころが傷つく状況から逃れられた。
不登校の原因が何であろうと親にできることは、
家庭で子どもがリラックスし過ごせるようにこころがけること。
★感想
涙がでた。
*もう一度引用*************
大人の怒りの言葉を聴いていると、
自分や自分の信念ではなく、自分の親を
守ろうとしているのではないか、
と感じられることある。
親の教えを守ろうとしているのではい。
親そのものを守らなければ、と強く感じている。
そして親を攻撃しようとする相手に対して
怒っているようなのだ。
********************
今こそ、決心したい。
不安や怒りの負の連鎖を自分が断ち切る。
子どもたちの未来には明るい連鎖を広げる。 - 投稿日:2025年01月12日
これは今後の子育てのバイブルになりそう。
小言を言うのをやめる…
めちゃくちゃ難しいけど、
試す価値はありそうだ。 - 投稿日:2024年09月07日
あなたが小さかったとき、一生懸命子育てしたことは、私の人生の宝物。
本当に大変だったけど、毎日がすごく幸せで、あなたが私の子どもだったという奇跡は、いくら感謝してもしきれないほど。
去られるためにそこにいる
題名が心を揺さぶる。
去られることになっても揺るがず、どっしりとしていられること、必要なときはいつでも温かく手を差し伸べる用意があること、そんな親になりたい。
親も不安ばかり、だから小言が多くなってしまう。
子どもにとっても、自分にとっても居心地のいい場所をつくろう。
小言を控えよう。
子どもの問題は何か大切な意味があるかもしれないと思って向き合おう。
もっと子どもや大切な人の話を聞いていこう。
またやってしまった、、と思ったら、気づいたところで立て直せばいい。
名著だ。
子どもへのまなざしにつながる。
お気に入り新着通知
- 未追加:
- 田中茂樹
ランキング:人文・思想・社会
※1時間ごとに更新
-
1

-
【入荷予約】半分論
村上 信五
1,980円(税込)
-
2

-
【予約】はらえば叶う! 神様に聞いた成…
大澤 美樹
1,705円(税込)
-
3

-
【入荷予約】「賢い子」の親が本当にやっ…
講談社
1,459円(税込)
-
4

-
17歳のときに知りたかった受験のこと、人…
びーやま
1,650円(税込)
-
5

-
DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる…
ビル・パーキンス
1,870円(税込)
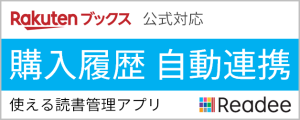



![去られるためにそこにいる子育てに悩む親との心理臨床[田中茂樹]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/3919/9784535563919_1_2.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![去られるためにそこにいる子育てに悩む親との心理臨床[田中茂樹]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/3919/9784535563919_2_2.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)


![去られるためにそこにいる子育てに悩む親との心理臨床[田中茂樹]](https://tshop.r10s.jp/book/cabinet/3919/9784535563919_1_2.jpg)