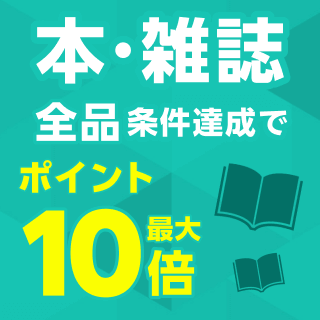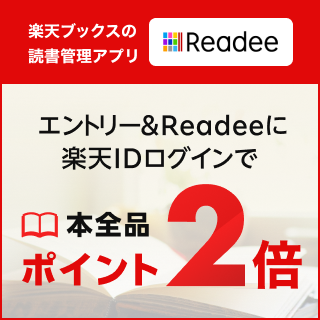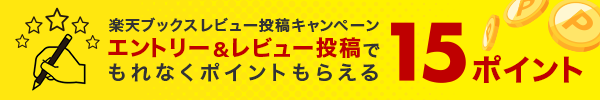- 現在地
- トップ > 本 > 新書 > 美容・暮らし・健康・料理
デジタル・ファシズム 日本の資産と主権が消える (NHK出版新書 655 655)
- | レビューを書く
968円(税込)送料無料
- 紙書籍 (新書)
- デジタル・ファシズム
- 968円
- 電子書籍 (楽天Kobo)
- デジタル・ファシズム 日本の資産と主権が消える
- 968円
この商品が関連するクーポン・キャンペーンがあります(10件)開催中のキャンペーンをもっと見る
※エントリー必要の有無や実施期間等の各種詳細条件は、必ず各説明頁でご確認ください。
- 【ポイント5倍】図書カードNEXT利用でお得に読書を楽しもう♪
- 【楽天ブックス×楽天ウェブ検索】条件達成で10万ポイント山分け!
- 本・雑誌全品対象!条件達成でポイント最大10倍(2025/3/1-3/31)
- 【対象者限定】全ジャンル対象!ポイント3倍 おかえりキャンペーン
- 【楽天モバイルご契約者様】条件達成で100万ポイント山分け!
- 条件達成で本全品ポイント2倍!楽天ブックスの読書管理アプリを使おう
- 【楽天ブックス×楽天ラクマ】条件達成で10万ポイント山分け!
- エントリー&お気に入り新着通知登録で300円OFFクーポン当たる!
- 楽天モバイル紹介キャンペーンの拡散で300円OFFクーポン進呈
- 【楽天24】日用品の楽天24と楽天ブックス買いまわりでクーポン★
商品情報
- 発売日: 2021年08月31日頃
- 著者/編集: 堤 未果(著)
- レーベル: NHK出版新書 655
- 出版社: NHK出版
- 発行形態: 新書
- ページ数: 288p
- ISBN: 9784140886557
この商品を買った人が興味のある商品
よく一緒に購入されている商品
商品説明
内容紹介(出版社より)
街も給与も教育も、米中の支配下に!?
コロナ禍の裏で、デジタル改革という名のもとに恐るべき「売国ビジネス」が進んでいるのをご存じだろうか?
アマゾン、グーグル、ファーウェイをはじめ米中巨大テック資本が、行政、金融、教育という、日本の“心臓部”を狙っている。
デジタル庁、スーパーシティ、キャッシュレス化、オンライン教育、マイナンバー……
そこから浮かび上がるのは、日本が丸ごと外資に支配されるXデーが、刻々と近づいている現実だ。
果たして私たちは「今だけ金だけ自分だけ」のこの強欲ゲームから抜け出すことができるのか?
20万部超のベストセラー『日本が売られる』から3年。
気鋭の国際ジャーナリストが、緻密な取材と膨大な資料をもとに暴く、「日本デジタル化計画」の恐るべき裏側!
内容紹介(「BOOK」データベースより)
行政、金融、教育。国の心臓部である日本の公共システムが、今まさに海外資本から狙われていることをご存知だろうか?コロナ禍で進むデジタル改革によって規制緩和され、米中をはじめとする巨大資本が日本に参入し放題。スーパーシティ、デジタル給与、オンライン教育…いったい今、日本で何が起きているのか?気鋭の国際ジャーナリストが緻密な取材と膨大な資料をもとに明かす、「日本デジタル化計画」驚きの裏側!
目次(「BOOK」データベースより)
第1部 政府が狙われる(最高権力と利権の館「デジタル庁」/「スーパーシティ」の主権は誰に?/デジタル政府に必要なたった一つのこと)/第2部 マネーが狙われる(本当は怖いスマホ決済/熾烈なデジタルマネー戦争/お金の主権を手放すな)/第3部 教育が狙われる(グーグルが教室に来る!?/オンライン教育というドル箱/教科書のない学校)
著者情報(「BOOK」データベースより)
堤未果(ツツミミカ)
国際ジャーナリスト。東京生まれ。ニューヨーク州立大学国際関係論学科卒、ニューヨーク市立大学大学院国際関係論学科修士号。国連、米国野村證券などを経て現職。『報道が教えてくれないアメリカ弱者革命』で黒田清・日本ジャーナリスト会議新人賞を受賞。『ルポ貧困大国アメリカ』で日本エッセイストクラブ賞、中央公論新書大賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
商品レビュー(73件)
- 総合評価
 3.85
3.85
ブックスのレビュー(9件)
-
国家による監視社会になってしまう!
- rakuraku..
- 投稿日:2021年09月07日
一見するとデジタル化した方が効率は良くなるように見えますが実はさらにその先には国民を監視することが可能な世界が見えて来ます。銀行にある預金残高はもちろん病院履歴や移動の履歴などすべて紐付けされると自分の行動が把握されてしまうので何でもデジタルにするのは考えものであると感じましたね。
4人が参考になったと回答
-
(無題)
- 楽天123456785520
- 投稿日:2023年03月16日
この本に書いてある内容は、知識として知っておくべき。
日本人の個人情報のサーバーを海外に置く時点で、日本人をデジタル植民地化している役人・政治家は国民を救う気がなくて、自分の利益が守られたらいいという考えしかもっていない。2人が参考になったと回答
-
(無題)
- tony6969
- 投稿日:2022年01月31日
書名のデジタル・ファシズムの内容がよくわからずに、わからないからこそ購入。要するに、デジタル庁が創設された日本は、デジタル改革のもと、アマゾン、グーグル、ファーウェイをはじめ米中巨大テック資本が、日本の心臓部を狙っているので、警戒を促し、日本の独立性を今一度再考すべきとしたのがこの本のメッセージと理解した。
2人が参考になったと回答
ブクログのレビュー(64件)
- 投稿日:2025年03月06日
デジタル化への加速はこの日本において良い方向に進んでいるだろうか、この書で疑問を持った。外部委託の寄せ集め集団でデジタル庁の大きな権限と予算は信頼できるシステムではない、と言う。それは便利になる裏返しで情報漏洩しかり、国民の了解無しの情報の管理体制だ。マイナーカード含め、現在個人情報の閲覧規定が無い、例えば本人の了解無しで関係者は閲覧できるが、本人が削除出来ず、データーの保管が国外にありセキュリティー保護規定も見えていない状況だ。このような無能な管理者・庁のデジタル化では利便性追求とは言え、今後恐ろしい権限政策となりうる。その他、世界のデジタルマネー変革である「グレード・リセット」による銀行間のプラットファーム:SWIFTからCIPSへの流れ、「米国ドル本位」離れが表面化しており、 IMF、中国、イスラム諸国、EU諸国など世界が動き始めている事は極めて重要だ。その中で元米国国務長官キッシンジャーの言葉「金融を支配すれば、全世界をコントロールできる」は不気味に映った。また、歴史学者のハワード・ジン氏「政府は必ず嘘をつく」(目的達成のため)が印象的だった。また、著者は「人間は権力を持つと腐敗する」を打破するためのデジタル政府が必須となる」故に「デジタル化における配慮で大切な事は、透明性、公平性、説明責任、憲法の遵守であるべきだ」としている。よって「真の危機はコンピューターが人間のような頭脳を持ってしまうことよりも、人間がコンピュータのように考え始めた時」にやって来る、と危機感を表している。
- 投稿日:2024年11月17日
公共サービス デジタル庁 についてどのような経緯で発足したのかはよくわからない
がセキュリティの甘さは今後 私たちの生活に不利益が発生する恐れがあると感じた
セーフサービスに米国の民間企業を利用登録させるのはいかがなものかと思う
デジタルセキュリティについて個人でどのように対応するのか 解決策は見いだせないままだ
金融について
キャッシュレス決済はここ数年 すごく多くなってきていると感じている
クレジットカードより利便性があると思える
どのような危険性があるのか 啓発する 意味合いでは 本書の記事は良いのかもしれない
クレジットカードについては 盲点を指適している
デジタル マネーについては 本書ではよくわからないだろう
竹中平蔵氏は本著者と相性が悪いようだ
米系GAFA
中国系BATH
デジタル教育 オンラインシステム 教育小学生中学生は学校で勉強した方が教室で皆集まって話した方がいいような気がする - 投稿日:2024年10月07日
若干、論理に飛躍があるように思います。
きっと、様々な事象を、筆者が言いたいことに結び付けたいがゆえの飛躍なのだと思いますが。
最近、思うのですが、国家は、100年先を見据えて、一年一年を重ねていくべき存在ではないかと。
その一方で、企業は、遠い未来のことは何ともいえないけれども、とにかく一年一年をしっかり積み重ねていくことを目指す存在なのではないかと。
同じように一年一年を重ねていくとしても、100年先を見据えた存在である国家と、一年一年が勝負の企業では、一年一年の重ね方が違うと思うのです。
国家が企業を活用する際には、一年一年の重ね方の違いを理解し、国家の考え方や姿勢に沿うように活用しないと、企業の論理に巻き込まれ、見据えたはずの100年先とは違う方向に進んでしまうと思うのです。
デジタル・ファシズムは、まさに、国家が企業の論理に巻き込まれた、あるいは巻き込まれつつある事象といえると思います。
選挙に勝つことが目的になりがちな政治家は、ある意味、企業と似た存在であり、100年先を考えて仕事に取り組むのは難しいと思われるので、100年先を考えて仕事に取り組めるはずの公務員が、あるべき日本、社会、将来を考え、進んでいくことができるような国家をつくることが大切なのではないでしょうか。
楽天ブックスランキング情報
-
 週間ランキング(2025年03月17日 - 2025年03月23日)
週間ランキング(2025年03月17日 - 2025年03月23日)
本:第-位( - ) > 新書:第2751位(↑) > 美容・暮らし・健康・料理:第470位(↑)
-
 日別ランキング
日別ランキング
ランキング情報がありません。
お気に入り新着通知
- 未追加:
- 堤 未果
ランキング:新書
※1時間ごとに更新
-
1

-
数学の言葉で世界を見たら
大栗博司
1,166円(税込)
-
2

-
【予約】独断と偏見(仮)
二宮 和也
1,100円(税込)
-
3

-
日ソ戦争
麻田雅文
1,078円(税込)
-
4

-
稼ぐ力は会計で決まる
山下明宏
990円(税込)
-
5

-
22世紀の資本主義 やがてお金は絶滅する
成田 悠輔
1,100円(税込)
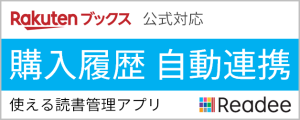



![デジタル・ファシズム日本の資産と主権が消える(NHK出版新書655655)[堤未果]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/6557/9784140886557_1_3.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![デジタル・ファシズム日本の資産と主権が消える(NHK出版新書655655)[堤未果]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/6557/9784140886557_2_2.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)


![デジタル・ファシズム日本の資産と主権が消える(NHK出版新書655655)[堤未果]](https://tshop.r10s.jp/book/cabinet/6557/9784140886557_1_3.jpg)