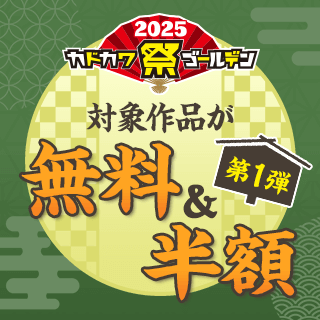商品情報
この商品を買った人が興味のある商品
商品説明
内容紹介
“歌聖”柿本人麻呂ーー宮廷権力と密接な関係にあった歌人が高らかに謡いあげたのは無邪気な叙景歌にすぎなかったのか? わが国最古の歌集『万葉集』の成立にメスを入れた時、初めて見えてきた、もうひとつの風景。韓国語・漢語を媒介にして古歌を読み解くことで「ますらをぶり」の歌風は大胆な変貌を遂げた。人麻呂の生涯を辿りつつ、しなやかな日本語研究への道を拓く問題の書。
商品レビュー(9件)
- 総合評価
 3.25
3.25
楽天Koboのレビュー
まだレビューがありません。 レビューを書く
ブクログのレビュー(9件)
- 投稿日:2022年05月19日
万葉集に数々の歌を残す柿本人麻呂は、多言語に長けた詩人であった。残された歌の一部は現代語訳がうまくなされていないことに目をつけ、朝鮮語(本文ママ)や中国語で解釈することによって、柿本人麻呂の晩年が明らかに…。
推理小説かと思って読み始めたんだよね。
それはさておき、最初の章からちょっと怪しいと言うか、偏見の入った解釈をしますよというポーズが見られ、早い話が「全部朝鮮語(本文ママ)で解釈することで何でも解ける」という話である。中国語(漢字)での解釈だと妙に悔しそうだ。
そういう偏見のもと、ドキュメンタリーと言うよりは、社会人大学のフィールドワーク風景で、仲間と会話をしながらというスタイルで話が進んでいく。
おそらく(本人は古典を読んだこともないと書いている)、素人の寄り合いに一人スーパーバイザーがいるという形で進んでおり、もともと大学等までの教育を受けていないだろうという雰囲気の人たちが多くでてくる。その弊害として、理系の学生にも多いのだが、スーパーバイザーが、本当の答えを知っていると思い込ませるような文章が続くので、読んでいて新規性があるのだか無いのだかがわからず、面白くもないしひたすら眠い。
新規のものを研究しているのなら、新規であることを前提に立てて書くべきで、「わかった」となったときの、スーパーバイザー"アガサ"の反応がなんとも腑に落ちないのだ。
途中からは、ほぼ漢字の分解と解釈という、普通そうだよなと言う話に。「石見で硯」「白水で泉」と大発見のように書いているが、そんなの江戸時代にもあり、現代のおっさんでも言うよね。とにかく浅い。
また、「地名は注意」と定義した割に、地名を現代の地名と当てはめてしまい、「兵庫県の云々」などと書いているが、本当にその時代にそんな狭い範囲を示すものだったんだろうか?
柿本人麻呂が渡来人であったとしても、別に面白みもないし、筆者は朝鮮と言うが、ほぼ中国の人と言ってよかったのではないかと、読みながら思った。
変な本だなと思っていたが、NHKが飛びついて、その後解釈が間違っていたことが明らかになったらしく、研究ってのは、先入観が強いほど失敗するよね、というよくある話である。
時間の無駄だった。 - 投稿日:2015年04月11日
学校の授業で習った万葉集の歌。ほとんどが叙景詩や叙情詩だと言われていましたが、漢字の意味や朝鮮語から全く違った解釈が出来ることにビックリし、とても興味深い内容でした。
- 投稿日:2012年10月25日
仮説を構築する というのは 重要な意味を持っている。
歴史を解明するためには、仮説なくして成り立たない。
歴史とは 『仮説』のつくり方で 方向が決まる。
多言語教育を受けた 若い人たちが
感性あふれる 言葉 に対する想いを 解き明かしていく。
果敢であることに・・・共感を覚える。
言葉から沸き立つ 質感 がどう形成されるのか?
中国、朝鮮、日本という 3つの国の中の底流に流れるものは?
はじめに・・・聖徳太子をこう表現する。
聖徳太子が 10人の話を聞くことができるというより
語学の天才であった という説明は 納得。
聖という 字 が 『耳』と『口』の『王』ということから、
聖となっている。
聖徳太子は日本書紀では・・・
厩戸皇子(うまやとのみこ)
厩戸豊聡耳皇子(うまやとのとよとみみのみこ)
豊聡耳法大王(とよとみみののりのおほきみ)
と呼ばれている・・・『耳』がよかったのだろう。
万葉集の謎の歌人 柿本人麻呂 の 詠んだ歌を
『朝鮮語』で、解明しようとする。
朝鮮語の辞典は
『李朝語辞典』(1979年)を使う。
(朝鮮語古語辞典というのがあるのだろうか?
書かれた当時は インターネットがなかったので、
重い辞典を運びながらの挑戦だったようだ。
万葉集から 人麻呂の歌
東 野炎 立所見而 反見為者 月西渡
東の野に炎(かぎろい)の立つ見えてかへり見すれば月傾きぬ
漢字の羅列を大和言葉に読み替えたのは・・・
すごい読解力といわざるを得ない。
それを、朝鮮語で読み替えることができるのか?
712年 古事記 720年 日本書紀
という 日本の歴史が作られる
日本語漢字のひとつの集約の時期である。
前夜に 柿本人麻呂 は、歌を歌っていた。
この時に 使われていたのは 万葉仮名。
万葉仮名 は 日本語になっていた。
万葉仮名を 中国語で詠めても 意味はなさない。
(この本では中国語の表記が ピンインを使わないのは残念。
万葉仮名は 漢字であっても 中国語ではない。
万葉仮名を 朝鮮の古代漢字でよんで、古代ハングル語にする
その意味が通じる という着眼点はありうることかもしれない。
倭語と朝鮮語の共通性がどこまであるかがであるが、
朝鮮の漢字がどんな風になっていたのか
そのことがわかってくるとみえてくるものがある。
いつくかの作業のポイントがある・・・
現在の朝鮮語でよむ・・・『時間軸のずれ』
古語としての朝鮮語でよむ
万葉当時の朝鮮語でよむ
人麻呂がなぜその当時の朝鮮語を知っていたのか?
柿本人麻呂は、出自が不明であることから、
朝鮮の渡来人・・・と推定していくのであるが・・
やはり、ちょっと無理がある。
人麻呂の歌だけでの推定では、『物的証拠』が少なすぎるのだ。
解釈の方法論ではなく、柿本人麻呂ののこした
暗号を違ったメッセージに仕立て上げると
おもしろい読み物になったとおもうが・・・
ダヴィンチコードのようなイメージが時代を広げて展開する。
楽天ブックスランキング情報
-
 週間ランキング
週間ランキング
ランキング情報がありません。
-
 日別ランキング
日別ランキング
ランキング情報がありません。
-
期間限定!イチオシのキャンペーン
電子書籍のお得なキャンペーンを期間限定で開催中。お見逃しなく!
ランキング:人文・思想・社会
※1時間ごとに更新
-
1

-
 大白蓮華 2025年4月号
大白蓮華 2025年4月号
大白蓮華編集部
224円(税込)
-
2

-
 絶対悲観主義
絶対悲観主義
楠木建
935円(税込)
-
3

-
 ひとはなぜ戦争をするのか
ひとはなぜ戦争をするのか
アルバート・アインシュタイン
660円(税込)
-
4

-
 1回1分! 本気(マジ)やせダイエット…
1回1分! 本気(マジ)やせダイエット…
まる
798円(税込)
-
5

-
 韓国人オッパが作る 家にある調味料で …
韓国人オッパが作る 家にある調味料で …
韓国人オッパ セミ
798円(税込)


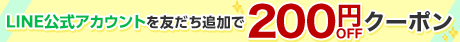




















 電子書籍版
電子書籍版