「未熟さ」の系譜ー宝塚からジャニーズまでー(新潮選書) (新潮選書) [電子書籍版]
周東美材
- | レビューを書く
1,705円(税込)
- 電子書籍 (楽天Kobo)
- 「未熟さ」の系譜ー宝塚からジャニーズまでー(新潮選書)
- 1,705円
- 紙書籍 (全集・双書)
- 「未熟さ」の系譜
- 1,705円
商品情報
この商品を買った人が興味のある商品
商品説明
内容紹介
若さや親しみやすさで人気を得るアイドル、ジュニアから養成されるジャニーズ、音楽学校入試が毎年報じられる宝塚歌劇団……成長途上ゆえのアマチュア性が愛好される芸能様式は、いかに成立したのか。近代家族とメディアが生んだ「お茶の間の人気者」から日本文化の核心を浮き彫りにする、気鋭の社会学者による画期的論考。
商品レビュー(3件)
- 総合評価
 4.00
4.00
楽天Koboのレビュー
まだレビューがありません。 レビューを書く
ブクログのレビュー(3件)
- 投稿日:2023年05月17日
近世の日本の芸能史を描きつつ、なぜ日本では未熟なものが愛されるのかを論考した本。
筆者は、大正以降の日本の家庭が子ども中心になり、子どもに受ける芸能をメディア(レコード、少女歌劇団、テレビなど)が提供したことを原因と結論づけているが、他にももっと大きな要因があるのではないだろうかと思ってしまう。
明治以前の日本にも未熟なものをこそ愛でる文化はあっただろうし、ジャニーズは最近話題になったジャニー喜多川氏による少年たちへの性加害を含む少年愛の目線、女性アイドルの性的消費、人権無視(恋愛禁止など…)、女性差別などの問題も影響があるように思える。
また、欧米や他のアジアの国々ではどうなのか…というところももっと知りたかった。 - 投稿日:2022年08月18日
KARAとか少女時代が日本のチャートでも活躍していた時代だったか…韓国のアイドルは「完成度」で勝負するのに対して日本のアイドルは「未成熟」を楽しむもの、という言説に出会ったことがあります。それは源氏物語で光源氏が若紫の成長するのを愛でるような体質が日本文化にそもそもあるからだ、というような指摘でした。その説が正しいのかどうかは検証するのが難しいと思います。しかし日本に資本主義が定着し消費社会が成立する時代にフォーカスを当てて芸能史を「未熟さ」をキーワードに分析する本書を読んで、研究としても掘りがいのあるテーマだと思いました。分析されるのは、童謡、宝塚、渡辺プロダクション、ジャニーズ、グループ・サウンズ、スター誕生!。特に童謡については知らないことだらけで驚きの連続。都市に生まれた新中間層の理想が「音楽のある家庭」であり、そこが童謡の「市場」だったという論には説得力がありました。今年読んだ貞包英之『サブカルチャーを消費する』ともリンクしました。さすがに著者が長年取り組んできたテーマです。一方、渡辺プロダクション以下のテーマについては、コンテンツを提供する側のストーリーに比して、享受する側の分析がもっと分厚くてもよかったかも。それぞれが繋がったら日本文化の「未熟さ」を愛でる文化へも肉薄できるかも、と思いました。さらなる論考の深堀を楽しみにします。
- 投稿日:2022年07月18日
「女・子ども」ウケする音楽が流行るのは日本だけであり、宝塚やジャニーズの存在理由を翻訳するのは困難が伴うようである(そもそもジャーニーズの成り立ちは男版宝塚を作ろうとしたのが出発点だったとは)。本書では大正・昭和の芸能史を辿りながら、「未熟さ」を基調とするポピュラー音楽を通じて近代日本とはなんであったのかを明らかにしてく。その際に重要となるキーワードが近代家族や「お茶の間」である。人種や民族や階級といった軋轢のない日本では、「子ども」という価値を重視し、それが異文化受容緩衝装置となり、近代家族の理想像としての「団欒」と結びつく事により、ポピュラー音楽が流行るという構造になっているようである。
しかしながら、さすがに平成に入りゼロ成長の時代と共に、人々の価値観・生き方や家族のあり方等も変化しつつあると思うが、世論調査では家族の団欒こそが家庭の役割であり、最も充実を感じる時であるとの結果となっており、「女・子ども」ウケする音楽は衰えることなく再生産が繰り返されている。中々人々の意識というものは変化しないものである。とはいえ、ネット社会進展や単身世帯の増加により実生活は変化している、昔に比べれば「団欒」は減っているだろうし、無論子供も減っている。よって、子供を重視する価値観や家族規範にも変化があるはずである。にもかかららず「未熟さ」を求める傾向に変化がないのであれば、これはもう所謂「日本人論」として別の要因を考えねばならない。よく日本はジブリアニメに顕著なように「ロリコン文化」と言われることがあるが、このような幼児的な未熟さを求める、しかもマスメディアが大々的に扱っても何の批判も起こらないというのは、どういうことなのか。今後の研究が進むことに期待したい。
楽天ブックスランキング情報
-
 週間ランキング
週間ランキング
ランキング情報がありません。
-
 日別ランキング
日別ランキング
ランキング情報がありません。
-
期間限定!イチオシのキャンペーン
電子書籍のお得なキャンペーンを期間限定で開催中。お見逃しなく!
ランキング:人文・思想・社会
※1時間ごとに更新
-
1

-
 大白蓮華 2025年4月号
大白蓮華 2025年4月号
大白蓮華編集部
224円(税込)
-
2

-
 あぶない法哲学 常識に盾突く思考のレッ…
あぶない法哲学 常識に盾突く思考のレッ…
住吉雅美
468円(税込)
-
3

-
 西洋の敗北 日本と世界に何が起きるのか
西洋の敗北 日本と世界に何が起きるのか
エマニュエル・トッド
2,800円(税込)
-
4

-
 アンネの日記 増補新訂版
アンネの日記 増補新訂版
アンネ・フランク
947円(税込)
-
5

-
 でっちあげー福岡「殺人教師」事件の真相…
でっちあげー福岡「殺人教師」事件の真相…
福田ますみ
649円(税込)


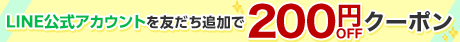
























 電子書籍版
電子書籍版

















