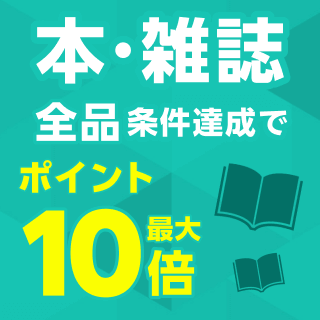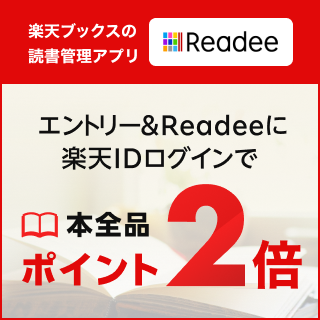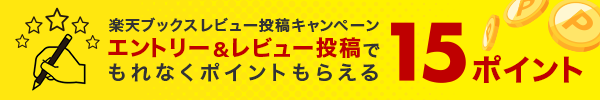思考技術 「答えのないゲーム」を楽しむ
- | レビューを書く
1,760円(税込)送料無料
- 紙書籍 (単行本)
- 思考技術
- 1,760円
- 電子書籍 (楽天Kobo)
- 思考技術
- 1,760円
この商品が関連するクーポン・キャンペーンがあります(10件)開催中のキャンペーンをもっと見る
※エントリー必要の有無や実施期間等の各種詳細条件は、必ず各説明頁でご確認ください。
- 【終了間近!】 【ポイント5倍】図書カードNEXT利用でお得に読書を楽しもう♪
- 【楽天ブックス×楽天ウェブ検索】条件達成で10万ポイント山分け!
- 【終了間近!】 本・雑誌全品対象!条件達成でポイント最大10倍(2025/3/1-3/31)
- 【終了間近!】 【楽天モバイルご契約者様】条件達成で100万ポイント山分け!
- 【終了間近!】 条件達成で本全品ポイント2倍!楽天ブックスの読書管理アプリを使おう
- 【終了間近!】 【楽天ブックス×楽天ラクマ】条件達成で10万ポイント山分け!
- エントリー&お気に入り新着通知登録で300円OFFクーポン当たる!
- 楽天モバイル紹介キャンペーンの拡散で300円OFFクーポン進呈
- 【楽天24】日用品の楽天24と楽天ブックス買いまわりでクーポン★
- Ulike タイアップ 202503030430
この商品を買った人が興味のある商品
よく一緒に購入されている商品
商品説明
内容紹介(出版社より)
ーー答え=正解のない課題にどう立ち向かうか?--
★3000人以上に「考え方」を教えてきた元戦略コンサルの著者が記す思考の秘訣!
★この1冊で「考えること」が楽しくなる!
★ベストセラー『変える技術、考える技術』『フェルミ推定の技術』の著者、待望の4冊目!
(本書の内容)
第1章「答えのないゲーム」の戦い方をしませんか?
▼「答えのないゲーム」にはこの3ルール
1「プロセスがセクシー」=セクシーなプロセスから出てきた答えはセクシー。
2「2つ以上の選択肢を作り、選ぶ」=選択肢の比較感で、“より良い”ものを選ぶ。
3「炎上、議論が付き物」=議論することが大前提。時には炎上しないと終われない。
第2章「示唆」
▼ファクトから示唆=メッセージを抽出するためのキーワード
1「見たままですが」
2「何が言えるっけ?」
3「それは何人中何人?」
第3章「B◯条件」
▼炎上を回避し、議論を健やかにする思考技術
1A(自分の意見)とB(相手の意見)を真っ向から対立させて議論してしまうと、「答えのない」ゲームにおいては、「水掛け論」になってしまう。
2だからB(相手の意見)を直接否定してはいけない。相手の意見を直接否定した瞬間に水掛け論に突入する。
3だからB(相手の意見)が○となる(成立する)「条件(b)」を提示して、その「条件」を否定(a)する。
第4章「ゲーム&ゲーム」
▼思考プロセス、問題解決プロセスを体得する
1論点を立てる。
2ファクトから示唆を抽出する。
3仮説をつくる。
4仮説を検証する。
第5章「5つのゲーム感覚」
▼「答えのないゲーム」とその先へ
1答えのないゲームVS答えのあるゲーム
2ボジョレー思考VSロマネコンティ思考
3理解ドリブンVS暗記ドリブン
4100分の70VS100分の3
5アーティストモードVSクリエイターモード
内容紹介(「BOOK」データベースより)
本書は「答えのない」ビジネスの現場、ひいては人生において、その時その場で、できる限り後悔のない選択ができるように「考える技術」を解説したものです。
目次(「BOOK」データベースより)
第1章 「答えのないゲーム」の戦い方をしませんか?-「答えのないゲーム」の戦い方・3ルール(「答えのないゲーム」とは何か?-「答えのあるゲーム」の戦い方をしていませんか?/「答えのないゲーム」の戦い方ー「答えがない」のだから、こうするしかない。 ほか)/第2章 示唆ーファクトから「示唆=メッセージ」を抽出する思考技術(「示唆」とは何者か?-ファクトを言うポンコツ、脱ポンコツ/「示唆」を身につけるための2つの口癖ー口癖が一番、行動が変わる ほか)/第3章 BO条件ー炎上を回避し、議論を健やかにする思考技術(「算数」の解説の上手い下手ー「正解」を投げつけるポンコツ/「公務員VSミュージシャン」-BO条件に慣れる時間「駆け落ちを回避する方法」 ほか)/第4章 ゲーム&ゲームー思考プロセス、問題解決プロセスを体得する(ゲーム&ゲームとは何か?-あなたには解けるか?/ゲーム&ゲームの解説1-ステップ1:論点を立てる ほか)/第5章 5つのゲーム感覚ー「答えのないゲーム」とその先へ(ボジョレー思考VSロマネコンティ思考ーエリートの罠/理解ドリブンVS暗記ドリブンーエリートの限界 ほか)
著者情報(「BOOK」データベースより)
高松智史(タカマツサトシ)
一橋大学商学部卒。NTTデータ、BCG(ボストン・コンサルティング・グループ)を経て「考えるエンジン講座」を提供するKANATA設立。本講座は法人でも人気を博しており、これまでアクセンチュア、ミスミ等での研修実績がある。BCGでは、主に「中期経営計画」「新規事業立案」「組織・文化変革」などのコンサルティング業務に従事。YouTube「考えるエンジンちゃんねる」の運営者でもある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
商品レビュー(56件)
- 総合評価
 3.74
3.74
ブックスのレビュー(7件)
-
ビジネスの参考になれば
- 購入者さん
- 投稿日:2023年01月14日
早速、読みました。まだ読みきっていませんが、
参考になることもあり、よかったです。1人が参考になったと回答
-
(無題)
- Hamayang
- 投稿日:2023年10月08日
答えのない課題に向き合う際に、ゲーム的な視点で仮説を立てていく思考法等が記載されており、
若手の技術者にはそれなりに参考になる書籍かなと思います。0人が参考になったと回答
-
中身がない
- 購入者さん
- 投稿日:2023年09月13日
少ない文字数と薄すぎる内容。
久しぶりにこんなレベルの本に出会いました。
返金してほしいくらいです。0人が参考になったと回答
ブクログのレビュー(49件)
- 投稿日:2025年03月05日
考え方のヒント。
選択肢をたくさんつくる。
見たままですが→何が言える?→何人中何人?
もし〜だったら賛成。だけど今回は〜ではないので反対です。
検証のプロセス
考えることは言葉を作ること。 - 投稿日:2025年02月02日
正解のない仕事を進めている限り、その仕事の終着点は必ず「議論」。時には「炎上」が付き物。なるほど、、、確かにそうだ!
戦い方のルールとしてこの大前提をもったうえで、どゃあどうすれば、相手を納得させる説明が出来て、自分の進めたい方向に進めることが出来るか?のテクニックを教えてくれる本。
・事実→何が言えるっけ?(示唆)→にもかか構文を使った対比
・B○条件 - 投稿日:2025年01月26日
答えのない仕事等に臨むにあたって、参考にしたいと思い、読んでみた。
答えがないものなので、
思考が凝っていること、2つ以上の答えでどちらが優れているか比較すること、議論ありきで考える必要があるということは心に留めていたいと感じた。
また、B○条件については、
議論をする上で相手に理解を示しながら、あるべき答えに導くことができる方法であると感じたので、
物事の進むべき方向として修正すべきと感じた際は反射的に使えるように、常日頃から意識したい。
お気に入り新着通知
- 未追加:
- 高松 智史
ランキング:人文・思想・社会
※1時間ごとに更新
-
1

-
頭のいい人だけが解ける論理的思考問題
野村 裕之
1,980円(税込)
-
2

-
ほどよく孤独に生きてみる
藤井 英子
1,540円(税込)
-
3

-
「賢い子」の親が本当にやっていること …
講談社
1,459円(税込)
-
4

-
つば九郎のぽじてぃぶじんせいそうだん。
つば九郎
1,100円(税込)
-
5

-
人生の経営戦略
山口 周
1,980円(税込)
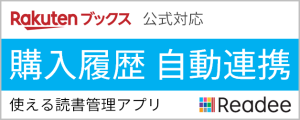



![思考技術「答えのないゲーム」を楽しむ[高松智史]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0005/9784408650005_1_4.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![思考技術「答えのないゲーム」を楽しむ[高松智史]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0005/9784408650005_2.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![思考技術「答えのないゲーム」を楽しむ[高松智史]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0005/9784408650005_3.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![思考技術「答えのないゲーム」を楽しむ[高松智史]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0005/9784408650005_4.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![思考技術「答えのないゲーム」を楽しむ[高松智史]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0005/9784408650005_5.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![思考技術「答えのないゲーム」を楽しむ[高松智史]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0005/9784408650005_6.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)






![思考技術「答えのないゲーム」を楽しむ[高松智史]](https://tshop.r10s.jp/book/cabinet/0005/9784408650005_1_4.jpg)