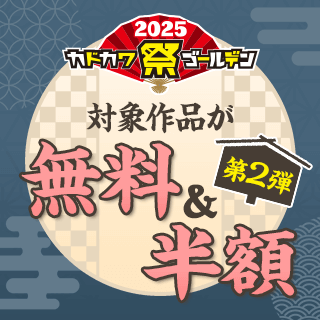商品情報
この商品を買った人が興味のある商品
商品説明
内容紹介
歯を食いしばり一日を過ごす。星を数える間もなく眠りにつく。都に献上する銅をつくるため、若き国人は懸命に働いた。優しき相棒、黒虫。情熱的な僧、景信。忘れられぬ出会いがあった。そしてあの日、青年は奈良へ旅立った。大仏の造営の命を受けて。生きて帰れるかは神仏のみが知る。そんな時代だ。天平の世に生きる男と女を、作家・帚木蓬生が熱き想いで刻みつけた、大河ロマン。
商品レビュー(27件)
- 総合評価
 4.19
4.19
楽天Koboのレビュー
まだレビューがありません。 レビューを書く
ブクログのレビュー(27件)
- 投稿日:2024年07月15日
2010年、平城京遷都1300年の記念すべき年に読んだ。
大仏建立の詔が聖武天皇によってなされたのは743年のことだ。
通常、大仏建立記は為政者の立場から、つまり聖武天皇•光明皇后•藤原仲麻呂•僧玄昉•行基の視点から語られる。
だが、本書は巨大大仏を実際に建立した一人の人夫の視点から描かれる。
市井の市民の視点を通すことで、時代背景がよりリアルに切実に感じられ、登場人物が生き生きと描かれることになるのだ。
主人公国人(くにと)に課せられた銅作りの苦役は悲惨極まりないが、その状況を易々と乗り越える主人公の心映えは純粋で美しい。
大仏建立に徴用され、長門国から奈良に向かうに当たっては、役人の庇護が有り安全に長旅をすることが出来る。
しかし、数年の苦役を辛うじて終えた後は、自助努力で故郷に帰りつかなくてはならないのだ、
使用価値のある間は大事にするが、使用価値が無くなった途端、国家権力は個人に無関心になる。
徴用された膨大な労働者によって大仏は建立されるが、労働が終わった後、労働者の殆どが、故郷に帰り着くことなく路傍に散っていったことを、歴史の教科書は教えない。
悲惨な物語にも関わらず、この小説が清々しいのは、主人公の無垢な心が色々なものを吸収して浄化し、周りの人々にも感化を与えていくからだ。
「大仏を作った者も仏」という悲田院の僧侶の言葉は、主人公の辿り着いた境地を語って感動的だ。
印象的に描かれるのは、行基上人の二人の弟子のコントラストだ。
ひとりは都から遠く離れた長門の国でたった一人巨大な磨崖仏を彫り上げる景信であり、今ひとりは豪華絢爛の中、物欲にまみえる大僧正だ。
ひとは、美しく生きることも、醜く生きることも出来る。
それを、市井の視点から、見事に描き切った大作だ。 - 投稿日:2024年04月16日
長門の国から石を切り出し銅を造り都に運ぶ。
大仏様をどうやって造りあげていったのか。
詳しく描かれた工程を読みながらもっと知りたい事は検索しながら読みました。
奈良の大仏様をこの本を読み終えてから、又この都を造りあげた関わった人々に対して参拝したいですね。感慨深い本です。 - 投稿日:2023年11月12日
極上の銅を命懸けで掘り出し、精錬して鋳込む。若き国人も仲間と共に都に向かった…。奈良の大仏造りに身を捧げ、報われずに散った男達の深き歓びと哀しみを描く大平ロマン。
楽天ブックスランキング情報
-
 週間ランキング
週間ランキング
ランキング情報がありません。
-
 日別ランキング
日別ランキング
ランキング情報がありません。
-
期間限定!イチオシのキャンペーン
電子書籍のお得なキャンペーンを期間限定で開催中。お見逃しなく!
ランキング:小説・エッセイ
※1時間ごとに更新
-
1

-
 淡海乃海 水面が揺れる時 外伝集~老雄…
淡海乃海 水面が揺れる時 外伝集~老雄…
イスラーフィール
1,320円(税込)
-
2

-
 カフネ
カフネ
阿部暁子
1,870円(税込)
-
3

-
 小学館ジュニア文庫 名探偵コナン 隻眼…
小学館ジュニア文庫 名探偵コナン 隻眼…
水稀しま
902円(税込)
-
4

-
 大阪・関西万博ぴあ
大阪・関西万博ぴあ
ぴあ
1,100円(税込)
-
5

-
 尊い5歳児たちが私に結婚相手を斡旋して…
尊い5歳児たちが私に結婚相手を斡旋して…
頼爾
715円(税込)


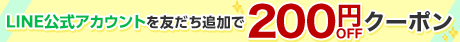





































































 電子書籍版
電子書籍版