明治維新の意味(新潮選書) (新潮選書) [電子書籍版]
北岡伸一
- | レビューを書く
1,925円(税込)
- 電子書籍 (楽天Kobo)
- 明治維新の意味(新潮選書)
- 1,925円
- 紙書籍 (全集・双書)
- 明治維新の意味
- 2,145円
商品情報
この商品を買った人が興味のある商品
商品説明
内容紹介
明治維新の大改革は、なぜあれほどスピード感をもって、果断に進められたのか。国連大使や国際協力機構理事長を務め、「ネーション・ビルディング」の難しさを知る政治学者が、いま改めて問う、制度作りとそれに関わる者たちのありかた。
商品レビュー(11件)
- 総合評価
 4.10
4.10
楽天Koboのレビュー
まだレビューがありません。 レビューを書く
ブクログのレビュー(11件)
- 投稿日:2025年01月17日
西洋では、絶えざる戦争がより強大な軍備を必要とし、それを支えるためにブルジョワジーに対して課税し、そのためにブルジョワジーの政治参加を認め、議会が成立するという流れがあった。日本では、徳川氏を中心とする盤石の態勢ができたために、それは起こらなかった。
明治維新から、内閣制度の創設、憲法の制定、議会の開設に至る変革は、既得権益を持つ特権層を打破し、様々な制約を取り除いた民主化革命、自由革命であり、人材登用革命であった。
明治6年の地租改正によって、作物の出来高に応じ、天候などに左右されていた税収は予測可能なものになった。地租は貧しい農民には重かったので、土地を手放すものが増え、一方で地主への土地集積が進んだ。土地を手放したものは職業を求めて都市に流入し、労働者になった。地租改正は、日本の資本主義の発展の不可欠の前提を作り出した。 - 投稿日:2024年09月15日
明治維新を否定的に捉える過激で感情的な原田伊織氏の本を読んだ後なので、北岡伸一氏の資料に基づく冷静な学者としての見解は対照的であった。
確かに倒幕は下級武士たちが権力奪取を狙ったクーデターであり、そこにテロリズムと言われるようなやり過ぎな行為もあったのだと思う。
ただ、若い下級武士の政権であったからこそ、廃藩置県、地租改正などで旧来の体制を完全に作り変える、短期間での富国強兵を実現できたのは間違いないと思う。また柔軟な思考で必死で勉強したからこそできた事。
大久保利通や伊藤博文といった優れたリーダーが、意志と能力のある人の意見を集めて手続き論や世論の支持は二の次として取り組んだのが明治維新の改革だった。
しかし統治機構が整うにつれ政治の制度化と合理化が起こり、強力なリーダーが出にくくなった。
そこでは多数をとることに優れたリーダーや組織の利益をもたらすリーダーが見識や能力に関わらず組織を率いる事になって行った事が、先の大戦での敗戦に繋がって行ったという。
創業者や建国者から代が進むにつれて組織がおかしくなるのは今も昔も同じ。
1945年の敗戦後、リーダー達が新しい日本を作り、70年以上の平和と経済的な繁栄をもたらした事は疑いようのない事実。
一方でGHQの息がかかった憲法や押し付けられた価値観に大きな影響を受けたのも事実。
世界は大きく変化しており、日本も変わらないといけないが、どちらの方向に進めば良いのだろう。
真に教養をもたないと判断を誤り、同じ歴史を繰り返す。 - 投稿日:2022年08月11日
近代日本の歩んできた道がわかりかけてきた。 西洋においては宗教が国家の基軸をなしているが我が国聞において基軸とすべきはひとり皇室あるのみ。この精神が、戦争に負けた日本をも支えている。
日本国憲法制定前後の政治状況についてもこの著作のように分かりやすく解説してほしい。
楽天ブックスランキング情報
-
 週間ランキング
週間ランキング
ランキング情報がありません。
-
 日別ランキング
日別ランキング
ランキング情報がありません。
-
期間限定!イチオシのキャンペーン
電子書籍のお得なキャンペーンを期間限定で開催中。お見逃しなく!
ランキング:人文・思想・社会
※1時間ごとに更新
-
1

-
 大白蓮華 2025年4月号
大白蓮華 2025年4月号
大白蓮華編集部
224円(税込)
-
2
![アンガーマネジメント超入門 「怒り」が消える心のトレーニング [図解] (特装版)](//tshop.r10s.jp/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9387/2000010299387.jpg?downsize=80:*)
-
 アンガーマネジメント超入門 「怒り」が…
アンガーマネジメント超入門 「怒り」が…
安藤俊介
200円(税込)
-
3

-
 いのちの地域ケア 第4版
いのちの地域ケア 第4版
松田正己
2,420円(税込)
-
4

-
 夫婦のトリセツ 決定版
夫婦のトリセツ 決定版
黒川伊保子
440円(税込)
-
5

-
 NEXUS 情報の人類史 上下合本版
NEXUS 情報の人類史 上下合本版
ユヴァル・ノア・ハラリ
4,400円(税込)


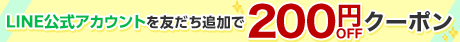






































 電子書籍版
電子書籍版







![アンガーマネジメント超入門 「怒り」が消える心のトレーニング [図解] (特装版)](http://tshop.r10s.jp/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9387/2000010299387.jpg?downsize=80:*)









