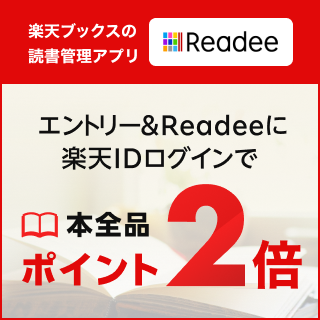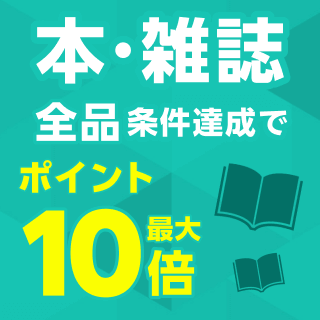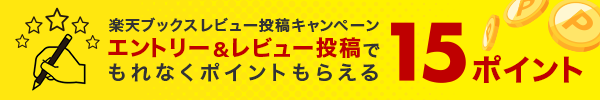失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織
- 紙書籍 (単行本)
- 失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織
- 2,530円
- 電子書籍 (楽天Kobo)
- 失敗の科学
- 2,530円
この商品が関連するクーポン・キャンペーンがあります(10件)開催中のキャンペーンをもっと見る
※エントリー必要の有無や実施期間等の各種詳細条件は、必ず各説明頁でご確認ください。
- 【楽天モバイルご契約者様】条件達成で100万ポイント山分け!
- 条件達成で本全品ポイント2倍!楽天ブックスの読書管理アプリを使おう
- 【ポイント5倍】図書カードNEXT利用でお得に読書を楽しもう♪
- 【楽天ブックス×楽天ラクマ】条件達成で10万ポイント山分け!
- 本・雑誌全品対象!条件達成でポイント最大10倍(2025/5/1-5/31)
- 【楽天Kobo】初めての方!条件達成で楽天ブックス購入分がポイント20倍
- 楽天モバイル紹介キャンペーンの拡散で1,000円OFFクーポン進呈
- エントリー&お気に入り新着通知登録で300円OFFクーポン当たる!
- 【楽天24】日用品の楽天24と楽天ブックス買いまわりでクーポン★
- 【楽天マガジン】楽天ブックスでのお買い物が全品ポイント10倍に!
商品情報
- 発売日: 2016年12月23日頃
- 著者/編集: マシュー・サイド
- 出版社: ディスカヴァー・トゥエンティワン
- 発行形態: 単行本
- ISBN: 9784799320235

商品説明
内容紹介



内容紹介(出版社より)
なぜ10人に1人が医療ミスの実態は改善されないのか ?
なぜ墜落したパイロットは警告を無視したのか ?
なぜ検察はDNA鑑定で無実でも有罪と言い張るのか ?
オックスフォード大を首席で卒業した異才のジャーナリストが、
医療業界、航空業界、グローバル企業、プロスポーツチーム…
あらゆる業界を横断し、失敗の構造を解き明かす !
■虐待事件で正義感に目覚めた市民が、
役所の失態を責め立てた結果、どうなったか?
■「ミスの報告を処罰しない」航空業界が
多くの事故を未然に防げている理由は?
■撃ち落された戦闘機に着目した天才数学者が、
戦闘機の帰還率向上をもたらした洞察とは?
■治療法が発見されていながらも、
「人類が200年放置し続けた病」があるのはなぜ?
<目次>
第1章 失敗のマネジメント
「ありえない」失敗が起きたとき、人はどう反応するか
「完璧な集中」こそが事故を招く
すべては「仮説」にすぎない
第2章 人はウソを隠すのではなく信じ込む
その「努力」が判断を鈍らせる
過去は「事後的」に編集される
第3章「単純化の罠」から脱出せよ
考えるな、間違えろ
「物語」が人を欺く
第4章 難問はまず切り刻め
「一発逆転」より「百発逆転」
第5章「犯人探し」バイアス
脳に組み込まれた「非難」のプログラム
「魔女狩り」症候群 そして、誰もいなくなった
第6章 究極の成果をもたらす マインドセット
誰でも、いつからでも能力は伸ばすことができる
終章 失敗と人類の進化
失敗は「厄災」ではない
内容紹介(「BOOK」データベースより)
誰もがみな本能的に失敗を遠ざける。だからこそ、失敗から積極的に学ぶごくわずかな人と組織だけが「究極のパフォーマンス」を発揮できるのだ。オックスフォード大を首席で卒業した異才のジャーナリストが、医療業界、航空業界、グローバル企業、プロスポーツチームなど、あらゆる業界を横断し、失敗の構造を解き明かす!
目次(「BOOK」データベースより)
第1章 失敗のマネジメント/第2章 人はウソを隠すのではなく信じ込む/第3章 「単純化の罠」から脱出せよ/第4章 難問はまず切り刻め/第5章 「犯人探し」バイアスとの闘い/第6章 究極の成果をもたらすマインドセット/終章 失敗と人類の進化
著者情報(「BOOK」データベースより)
サイド,マシュー(Syed,Matthew)
1970年生まれ。英『タイムズ』紙の第一級コラムニスト、ライター。オックスフォード大学哲学政治経済学部(PPE)を首席で卒業後、卓球選手として活躍し10年近くイングランド1位の座を守った。英国放送協会(BBC)『ニュースナイト』のほか、CNNインターナショナルやBBCワールドサービスでリポーターやコメンテーターなども務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
商品レビュー(288件)
- 総合評価
 4.50
4.50
ブックスのレビュー(19件)
-
(無題)
- 購入者さん
- 投稿日:2022年09月03日
ほんとに小説のように面白いです。買って損はない一冊でした。、
1人が参考になったと回答
-
(無題)
- 希望0301
- 投稿日:2022年02月28日
読み応えのある内容で、自分の仕事と照らし合わせながら読みました。
1人が参考になったと回答
-
良い本をありがとうございます。
- 岩馬
- 投稿日:2021年09月27日
非常に勉強になる本でした。今後活かしていきたい。
1人が参考になったと回答
ブクログのレビュー(269件)
- 投稿日:2025年04月16日
本書をAmazonでおすすめされていたかでたまたま見かけ、借りてみた気がする。本書は、『Black Box Thinking: The Surprising Truth About Success』を日本語訳したもので、失敗を科学的に考察したものと捉えている。一通り、ざっと読んだところではあるが、失敗から学ぶことの大切さ、特に人命に関わるような業界ではその重要さを認識した。仕事においても、先人の失敗を聞いて、自分の業務に生かせると効率的に働けるのかなと思った。
【メモ】
1. 失敗のマネジメント
2. 人はウソを隠すのではなく信じ込む
3. 「単純化の罠」から脱出せよ
4. 難問はまず切り刻め
5. 「犯人探し」バイアスとの闘い
6. 究極の成果をもたらすマインドセット
7. 失敗と人類の進化 - 投稿日:2025年03月06日
◆所感
失敗こそ成長に繋がる糸口。失敗は居た堪れない気持ちから曲解したくなるものだが、敢えて素直に認められる人に自分が率先してなるべきだし、メンバー含めてそういう組織にしたい。
そのため、以下2点に取り組む。
・失敗を振り返れる様にデータで定量的に可視化すること(歩留まり分析によるRC力の可視化やAGボトルネックの特定)
・失敗しても矢面に立ちチャレンジすることが讃えられる環境を作ること(褒めや定性評価)
◆学び
・あらゆることが当てはまるということは、何からも学べない。
常に通説を疑い、反証を立てることこそ成長に繋がる。科学には進歩があるが、宗教やイデオロギーは不変であるが故に、争いの種となる。自身が信じて疑わない当たり前こそ反証し続けるべき。
・失敗は浅いうちに認めておくべき。
認知的不協和により、サンクコストをかけるほど、時間が経つほど、組織で上の立場になるほど、無謬主義(自分たちの思想に間違いはないという考え)的な思想に陥りがちである。
・客観的なデータを如何に取り、参照するかで課題が見える。
明確に間違えた、正しかったと示せる状態にすること。データを参照して、判断の是非を問う機会を作り続けることが大事。
・犯人探しや非難ではなく、失敗から学べる組織にすべき。
人は一番単純で直感的な結論を出す傾向にある。ただし、物事は得てして複雑。非難ではなく、組織として失敗から学ぶことに注力すべき。 - 投稿日:2025年03月05日
興味深い実際の事例をもとに序盤は面白いと思ったが、時間をかけて読んでしまったこともあり疲れて読めなしなってしまった。参考になる考方は多く書かれている印象だった。
お気に入り新着通知
- 未追加:
- マシュー・サイド
ランキング:人文・思想・社会
※1時間ごとに更新
-
1

-
17歳のときに知りたかった受験のこと、人…
びーやま
1,650円(税込)
-
2

-
るるぶ大阪・関西万博へ行こう!
JTBパブリッシング 旅行ガイドブック 編…
1,320円(税込)
-
3

-
ほどよく孤独に生きてみる
藤井 英子
1,540円(税込)
-
4

-
財務省の秘密警察~安倍首相が最も恐れた…
大村大次郎
1,540円(税込)
-
5

-
【入荷予約】頭のいい人だけが解ける論理…
野村 裕之
1,980円(税込)
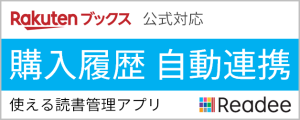


![[エンタメ市!] 全ジャンル対象! 条件達成で50万ポイント山分け!さらに先着限定クーポン配布中!](https://image.books.rakuten.co.jp/books/img/bnr/event/campaign/multi-buy/20241001/950x55.png)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_1_2.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_2.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_3.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_4.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_5.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_6.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_7.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_8.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_9.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_10.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_11.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_12.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_13.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_14.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_15.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_16.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_17.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)

















![失敗の科学失敗から学習する組織、学習できない組織[マシュー・サイド]](https://tshop.r10s.jp/book/cabinet/0235/9784799320235_1_2.jpg)